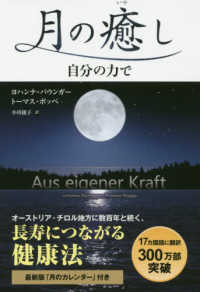出版社内容情報
福島第一原発事故から五年。脱原発への決定的理論、ついに誕生。
福島第一原発事故から五年、ついに脱原発への決定的理論が誕生した。
科学、技術、政治、経済、歴史、環境などあらゆる角度から、かつてない深度と射程で論じる巨編。
***
自ら生み出した「核=原子力」技術により、人類は絶滅の危機を迎えた。その危機が切迫していること、危機を回避するための哲学を持つべきことを、本書は明確に示す。(小出裕章)
福島原発事故によって、我々は原子力のもつ本質的問題に直面している。本書は、脱原発によって、「管理された民主主義」が支配する日本社会を、分権的で直接民主主義的な根源的民主主義にもとづく社会へと変えることができると説く。(大島堅一)
序論
第一部 原発と核兵器
第一章 核アポカリプス不感症の現状――ギュンター・アンダースから福島第一原発事故後の状況を考える
1 核の「軽視」の反復――一九五四年、一九七九年、二〇一一年
2 自由意志の彼岸
3 原子力=核事故は「戦争」とのみ比較可能である
4 福島第一原発事故後からアンダースを捉え直す
4‐1 原発と核兵器
4‐2 「ありえない」という呪文を自らに禁じること
4‐3 核アポカリプス不感症の深刻化
第二章 原子力発電と核兵器の等価性――フーコー的「権力=知」の視点から
1 原子力発電と核兵器の等価性
2 国家的技術システムとしての核兵器
3 原子力発電と核武装
第三章 絶滅技術と目的倒錯――モンテスキュー、ナンシーから原子力=核技術を考える
1 二つの近代技術論――モンテスキュー『ペルシア人の手紙』
1‐1 『ペルシア人の手紙』における二つの技術論
1‐2 『ペルシア人の手紙』を現在時から再読する
2 「範例」としてのフクシマ、ヒロシマ
2‐1 三つの論点――絶滅技術、国家と資本、技術革新
2‐2 「範例」としての福島第一原発事故――ジャン=リュック・ナンシーの視点
3 人間的生を目的と考えること
第二部 原発をめぐるイデオロギー批判
第一章 低線量被曝とセキュリティ権力――「しきい値」イデオロギー批判
1 避難区域の設定とセキュリティ権力
2 低線量被曝の影響評価と権力=知
3 放射能汚染と避難の権利
第二章 予告された事故の記録――「安全」イデオロギー批判?T
1 事故は予告されていた
1‐1 「原発震災」は予告されていた
1‐2 津波による被害は「想定外」ではない
2 伊方原発訴訟と「想像力の限界」
2‐1 地震想定の過小評価
2‐2 事故想定の過小評価
2‐3 原発事故の被害予測と「想像力の限界」
第三章 ノーマル・アクシデントとしての原発事故――「安全」イデオロギー批判?U
1 「確率論的安全評価」批判
1‐1 フォールト・ツリー解析の欠陥
1‐2 共通原因故障
2 ノーマル・アクシデントとしての原発事故
2‐1 複雑な相互作用
2‐2 緊密な結合
2‐3 どの技術を廃棄するか
第三部 構造的差別のシステムとしての原発
第一章 電源三法と地方の服従化
1 電源三法とは何か
2 構造的差別のシステムとリスクの偏在
3 核エネルギー政策に対する脱服従化
第二章 『原発切抜帖』が描く構造的差別
1 『原発切抜帖』という映画
2 『原発切抜帖』における「周縁」への眼差し――山上徹二郎の証言
3 グローバルな規模での周縁地域への構造的差別
4 原発労働者への構造的差別
第三章 構造的差別の歴史的「起源」――電力、二大国策、長距離発送電体制
1 「戦前」の日本電力事業史の見取り図――橘川武郎の時代区分
2 二大国策と長距離発送電体制をめぐって
3 症例としての東京電燈
3‐1 土台としての「富国強兵」と「殖産興業」
3‐2 長距離発送電体制による構造的差別
第四部 公害問題から福島第一原発事故を考える
第一章 足尾鉱毒事件と構造的差別
1 回帰する鉱毒とその否認
2 足尾鉱毒事件における差別の構造
2‐1 歴史的・地勢的条件による周縁性
2‐2 差別の深刻化とその背景
2‐3 差別の多重構造
2‐3‐1 「鉱都=企業城下町」の繁栄
2‐3‐2 加害と被害、五つの断面
3 足尾鉱毒被害の歴史的条件――田中正造と日露戦争
第二章 回帰する公害、回帰する原発事故
1 「戦後日本」の公害に関する一視角
1‐1 「戦後」の経済成長主義に見られる三重化された否認
1‐2 四大公害の歴史的「起源」から見た高度経済成長
1‐2‐1 イタイイタイ病
1‐2‐2 四日市公害
1‐2‐3 水俣病
1‐3 水俣病事件と福島第一原発事故の類似性
2 公害の否認としての「国土開発計画」――『資料新全国総合開発計画』を読む
3 原発事故の回帰、自己治療の切迫性
第三章 公害、原発事故、批判的科学
1 レイチェル・カーソンの文明批評
2 「公害という複雑な社会現象」――宇井純の科学批判
3 「科学の中立性」というイデオロギー――津田敏秀、アドルノ=ホルクハイマー
結論 脱原発の哲学
1 脱原発、脱被曝の理念
1‐1 脱原発、脱被曝の理念の切迫化――ハンス・ヨナス、ジャック・デリダ
1‐2 多様なる脱被曝の擁護
1‐3 「帰還」イデオロギー批判
2 脱原発の実現と民主主義
2‐1 脱原発をどのように実現すべきか
2‐2 脱原発によってどのような社会を実現すべきか
人名索引
【著者紹介】
佐藤嘉幸(さとう・よしゆき) 1971年、京都府生まれ。筑波大学人文社会系准教授。京都大学大学院経済学研究科博士課程を修了後、パリ第10大学にて博士号(哲学)取得。著書に、Pouvoir et resistance : Foucault, Deleuze, Derrida, Althusser,(L’Harmattan, 2007)、『権力と抵抗――フーコー・ドゥルーズ・デリダ・アルチュセール』(人文書院、2008年)、『新自由主義と権力??フーコーから現在性の哲学へ』(人文書院、2009年)。訳書にジュディス・バトラー『権力の心的な生?――主体化=服従化に関する諸理論』(清水知子との共訳、月曜社、2012年)、ミシェル・フーコー『ユートピア的身体/ヘテロトピア』(水声社、2013年)。
内容説明
福島第一原発事故から五年、ついに脱原発への決定的理論が誕生した。科学、技術、政治、経済、歴史、環境などあらゆる角度から、かつてない深度と射程で論じる巨編。
目次
序論
第1部 原発と核兵器(核アポカリプス不感症の現状―ギュンター・アンダースから福島第一原発事故後の状況を考える;原子力発電と核兵器の等価性―フーコー的「権力=知」の視点から;絶滅技術と目的倒錯―モンテスキュー、ナンシーから原子力=核技術を考える)
第2部 原発をめぐるイデオロギー批判(低線量被曝とセキュリティ権力―「しきい値」イデオロギー批判;予告された事故の記録―「安全」イデオロギー批判1;ノーマル・アクシデントとしての原発事故―「安全」イデオロギー批判2)
第3部 構造的差別のシステムとしての原発(電源三法と地方の服従化;『原発切抜帖』が描く構造的差別;構造的差別の歴史的「起源」―電力、二大国策、長距離発送電体制)
第4部 公害問題から福島第一原発事故を考える(足尾鉱毒事件と構造的差別;回帰する公害、回帰する原発事故;公害、原発事故、批判的科学)
結論 脱原発の哲学
著者等紹介
佐藤嘉幸[サトウヨシユキ]
1971年、京都府生まれ。筑波大学人文社会系准教授。京都大学大学院経済学研究科博士課程を修了後、パリ第10大学にて博士号(哲学)取得
田口卓臣[タグチタクミ]
1973年、神奈川県生まれ。宇都宮大学国際学部准教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程修了。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hitotoseno
Mealla0v0
ますたけ
ますたけ
-
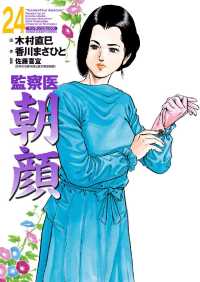
- 電子書籍
- 監察医朝顔 - 24巻