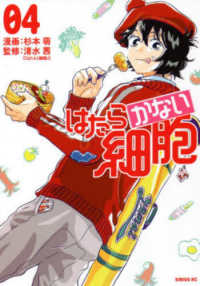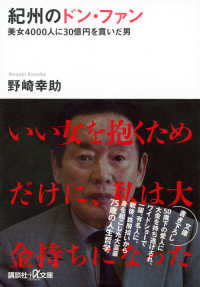内容説明
権力のあり様を分析し、「真実の生」の意義を説いたこのエッセイは、冷戦体制下の東欧で地下出版の形で広く読まれただけでなく、今なおその影響力はとどまることを知らない。形骸化した官僚制度、技術文明の危機を訴える本書は、私たち一人ひとりに「今、ここ」で何をすべきか、と問いかける。無関心に消費社会を生きる現代の私たちにも警鐘をならす一冊。解説、資料「憲章77」を付す。
目次
力なき者たちの力
資料 憲章七七
著者等紹介
阿部賢一[アベケンイチ]
1972年東京生まれ。東京外国語大学大学院博士後期課程修了。パリ第四大学(DEA取得)、カレル大学で学ぶ。現在、東京大学人文社会系研究科准教授。専門は、中東欧文学、比較文学。訳書オウジェドニーク『エウロペアナ』(共訳、白水社、2014)で第一回日本翻訳大賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
74
日々積み上げる心底の「真」。如何にこの軸を、様々な関係性の中で熟成させることができるのか?その手段の1つが『憲章77』。問題は、関係性醸成のための”架け橋”が、必ずしも真摯に機能せず歪曲すること。青果店の事例が、文字の齎す潜在性を示唆。隠れ蓑となり、抑制力ともなる功罪。大なり小なりの同調圧力が、大義となる感がうすら寒い。1978年に本著執筆。40数年前から現在にも続く著者の思いを読後に再考。故のディシデント也。プラハの春から『憲章77』を経て大統領。任期満了で政界引退した潔さにも共感。2021/12/10
ころこ
46
チェコの民主化運動の指導者であり、後年に大統領に就任した人物の文章という意味が最も大きい。言葉が現実と闘い政治的であっても結果が客観的に示されることは、自分の身を晒しているという一点において凄いことだ。プラハの春以後であり「ポスト全体主義」という言葉が使われているが、ソ連による規律権力による統制である。八百屋の店主のエピソード以外は政治哲学の硬い文章で、反権力の運動に留まっていて、文章上では新たな発見はなかった。対抗的な象徴的人物が大統領になることは人々に夢を見させるが、現実にも向き合わなければならない。2024/09/16
燃えつきた棒
45
1989年4月、改革派だった胡耀邦元総書記の死をきっかけに中国で民主化運動が発生する。 天安門事件の幕開けである。 同年6月、ポーランドに、10月、ハンガリーに非共産党国家が成立。 11月、ベルリンの壁崩壊、チェコスロヴァキアのビロード革命。 12月、ルーマニアのチャウシェスク政権崩壊。 そしてついに、ソビエト連邦が、成立から69年後の1991年12月に崩壊した。 89年は、激動の年だった。 だが、民主化運動を武力鎮圧して、中国だけが変わらなかった。/2021/01/05
Tai
24
ポスト全体主義体制は、統一、単一性、規律へと向かい、イデオロギーは自分はアイデンティティも威厳もある倫理的な人間であると人々に錯覚させる。逆に生はその本質において、複雑性、多様性、独立した自己形成や自己編成、自由の実現に向かう。民主主義も技術文明、産業社会、消費社会に振り回され無力状態にあり深い危機に直面している。社会の倫理的な再建は人間的な内実を起点とする構造の制度化から生まれるだろう。それは信頼、寛容さ、責任、連帯、愛という諸価値を回復すること。あるコミュニティは意義深いという共通の感情が共有される。2022/05/20
Nobuko Hashimoto
23
ひたすらどんどん本を読んでいく授業で、理論や思想に関心のある学生が、Eテレの「100分de名著」を見て興味を持ち、原典に挑戦しようと取り上げてくれた。私も一緒に読んだが、かなり苦戦。丸一日苦しみながら読んだ。ハヴェルは読みにくいのよ…でも、やっぱり、まずは自分で頭を抱えながら、読み解こうとすることが大事だなと、あらためて思った。と言いながら「100分de名著」の他の回のテキストも買いそうになっているけど(笑) 内容については…まとめる余力が残っていないのでパス!2021/01/13
-
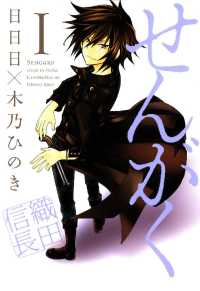
- 電子書籍
- せんがく(1) 月刊コミックアヴァルス
-
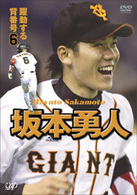
- DVD
- 坂本勇人 躍動する背番号6