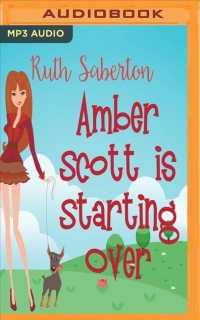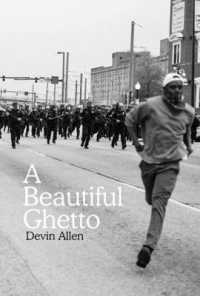内容説明
新たなドゥルーズ研究が始まる―焦点となるのは、ドゥルーズ哲学前期ともいうべき、『経験論と主体性』(1953年)から『差異と反復』(1968年)までの15年間。その間の著作を、時間軸に沿って綿密に検討し、ドゥルーズ哲学の中心を「能力論」と見定めることで、後期にまで及ぶ思想全体を根底から読み解く。次世代の研究の幕開けを告げる、新鋭による渾身作。
目次
第1部 超越論的経験論の生成(経験の超出―ヒュームの想像力/カントの能力論;経験の条件―ベルクソンの直観と記憶;超越論的経験論の産声―プルーストにおける超越論的感性論の統合)
第2部 超越論的経験論の構造(能力の超越的行使―“経験の条件”の転換;問題としての理念―潜在的なものの現働化の第三ヴァージョン;習得の時間、習得する自己―生成する経験の構造)
補論 スキゾ分析とリトルネロ―フェリックス・ガタリのプルースト論(スキゾ分析について;リトルネロについて)
著者等紹介
山森裕毅[ヤマモリユウキ]
1980年兵庫県生。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。現在、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター招聘研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なっぢ@断捨離実行中
8
浅田彰に「退屈な優等生」と罵倒されかねない几帳面な議論をしてるけど、ここまで噛み砕いてくれないとドゥルーズなんてわからんよ。ガタリとの繋がりがプルースト論と知れたのが一番の収穫。ラカン派の保守的なソシュール主義を打破すべく言葉の「リズム」を持ち出す点はまんまルジャンドルってか佐々木中だな。記憶の専制から生成の場へと解き放っていくプルーストの読みは過去の抑圧を特権化しがちな精神分析への批判にもなっている。ただこの手の美的アナキズムが資本主義への有効な批判ないし対抗策になり得てるかは議論が分かれるところ。2017/08/28
Bevel
8
プルースト論をベルクソンの批判として読み、『差異と反復』との結び付きを問うた部分が面白いなと思った。持続における記憶の内容の現動化だけでなく、さらに動的な習得のための過去の即自的存在の現動化を説明するものとしてプルースト論を読む。分有される本質を批判して、理性と記憶と感性を横断する「問題」概念への導入としてプルースト論を読む。このイメージは非常に明快で、著者のいうような「地味」なんかではまったくないと思った。2013/10/09
はすのこ
6
論理が可視化されており、文章が追いやすい。2016/11/11
hitotoseno
6
ドゥルーズのデビュー作から出世作までを丹念に追いかけた手堅い研究書。ドゥルーズのカント論は通常、「敵」について書いた物だから踏み台に過ぎないとされやすいが、そこで書かれている能力論を読んで、実のところドゥルーズ自身枠組みを受け継ぐという点でカントに負うところが大きいという証なのではないか、と思っていたので、自説を補強してもらった気になれた。初期ドゥルーズにおいては超越の契機こそ重要となる。記憶論も時間論も、人間の持ち分を越える体験について語ったものだからだ。2016/03/08
5
再読。めちゃくちゃいいっす。國分なんかよりいいかも。というかこういう本を研究書の値段ではなくて、手頃な値段で広く読めるようになればなあと思う。ドゥルーズの哲学を一言「習得」の過程の哲学である、と言い切って無闇にアンオプ、ミルプラに手を広げないのがまずいい。議論がクリアになっている。興味深いのはドゥルーズ のカント理解の断絶を読み込んでいるところで、むしろ単純なカントの否定/乗り越えになっていないことを指摘している所が面白い。2024/01/25