出版社内容情報
約110年前、大正5年(1916年)の1万分の1の地図と、約140年前の明治16~17年(1883~1884)年の詳細地図に地形の立体表現を施したオリジナル地図で、東京の街を見てみよう! 約70×48cmの大判大正地図つき!
●どんな時代の地図?
大正デモクラシーの頃の東京、そして明治維新から西南戦争が終結して6~7年、急速に社会が変化していた頃の東京は、どんな姿をしていたんだろう? 凸凹地図で各地を見て行くと、その後の時の流れも感じることができ、歴史を地理と結びつけて理解できます。
●気になる見どころ
・第一次世界大戦のころの日本の軍隊関連施設
・元勲や華族の邸宅
・庶民が住んでいた地形に共通点がある?
・川や堀がたくさん!
・山手線の上野~神田が未開業
・東京駅が開業直後
・現在の幹線道路、当時はなかったものも多数
ほか、盛りだくさん!
●大判地図が付属!
70cm×48cmの1万分の1大判地図も付属するので、都心の全貌を俯瞰でき、好きな場所を好きなだけ眺めることができます。
●章立てと掲載エリア
第1章 のどかさの残る渋谷・新宿・池袋
渋谷・青山/原宿・明治神宮建設地/新宿(南)/新宿(北)/池袋・雑司ヶ谷
第2章 「水の都」かつての江戸中心部
東京駅・京橋/丸の内・京橋/銀座・築地/御茶ノ水・水道橋/上野・本郷
第3章 丘の上のお屋敷と低地の庶民
永田町・赤坂/目白台・早稲田/千石・大塚/六本木・麻布台/三田・南麻布/高輪・五反田
第4章 「軍都」東京の実態
赤坂・六本木/北の丸・番町/四谷・曙橋/渋谷・駒場/恵比寿・中目黒/戸山・大久保
第5章 今はなき驚きの大規模施設
目黒・元競馬場/蔵前・神田佐久間町
【目次】
内容説明
新宿2丁目は牧場からの荒れ地、市谷や後楽園は軍事関連施設、華族は都心に広大な邸宅、池袋には田んぼ。地形を特徴とした施設の変遷を凸凹地図で読み取る!大正5年の大判地図(70cm×48cm)付。
目次
第1章 のどかさの残る渋谷・新宿・池袋(【大正】渋谷・青山 渋谷駅前に小学校と渋谷川、坂上には陸軍監獄;【大正】原宿・明治神宮建設地 天皇と海軍元帥が祭神の神社が創建される地 ほか)
第2章 「水の都」かつての江戸中心部(【大正】東京駅・京橋 丸の内側と八重洲側とで様相が一変する東京駅周辺;【明治】丸の内・京橋 広大な大名屋敷が並んでいた江戸の町の中枢部が維新で激変 ほか)
第3章 丘の上のお屋敷と低地の庶民(【明治】永田町・赤坂 地形上の超一等地に、大久保利通ら権力者の大邸宅;【大正】目白台・早稲田 総理大臣経験者の大邸宅が、神田川を見下ろす丘に並ぶ ほか)
第4章 「軍都」東京の実態―連隊、軍学校、兵器工場(【大正】赤坂・六本木 「軍都」東京の中枢エリア 伝統ある連隊、師団司令部が立地;【大正】北の丸・番町 近衛師団司令部、旧江戸城本丸と麹町の谷 ほか)
第5章 今はなき驚きの大規模施設(【大正】目黒・元競馬場 日本ダービーも開催された競馬場が山手線の駅近くに;【明治】蔵前・神田佐久間町 櫛形の船入り堀が異彩を放つ江戸ゆかりの米蔵)
著者等紹介
内田宗治[ウチダムネハル]
フリーライター、地形散歩ライター、鉄道史探訪家。1957年東京生まれ。実業之日本社で経済誌記者、旅行ガイドブックシリーズ編集長などを経てフリーに。アニメ映画『天気の子』(新海誠監督)での地形を活かしたロケハン協力なども行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
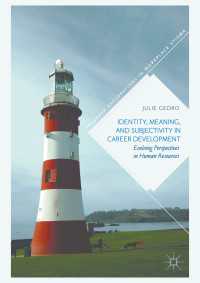
- 洋書電子書籍
- キャリア開発におけるアイデンティティ、…




