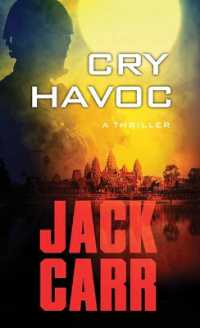内容説明
時は平安中期。京で心に荒ぶるものを抱いていた貴公子・藤原隆家は、陰陽師・安倍晴明から「あなた様が勝たねば、この国は亡びます」と告げられる。叔父・藤原道長との熾烈な政争を経て、九州大宰府へ赴いた隆家を待っていたのは、大陸の異民族「刀伊」の襲来だった―直木賞作家が実在した貴族の知られざる戦いを描く、絢爛たる戦記エンターテインメント巨編!
著者等紹介
葉室麟[ハムロリン]
1951年北九州市小倉生まれ。西南学院大学卒業後、地方紙記者などを経て、2005年『乾山晩愁』で歴史文学賞を受賞し、作家デビュー。07年『銀漢の賦』で松本清張賞を受賞。12年『蜩ノ記』で第146回直木賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yoshida
144
平安中期の藤原家の政争、そして異民族「刀伊」との闘いを中関白家の公卿である藤原隆家を中心に描く。躍動感溢れながらも、平安中期の文化や世相がしっかりと描かれている。天皇家の外戚として権勢をふるう為の藤原家内の争いや清少納言の機知に富んだ姿等興味深かったです。後半は女真族こと「刀伊」が対馬や壱岐、そして北九州を襲う。大宰権師に任官していた藤原隆家は「刀伊」を難戦の末に追い払う。異民族の侵略は元寇が有名であるが、「刀伊入寇」は初めて知った。大陸に近い日本海側では規模の差はあれど同様の事はあったのだろうと感じた。2016/05/07
麦ちゃんの下僕
138
オーディオブック+文庫本。エリート貴族でありながら武勇に優れ、九州に襲来した異民族「刀伊(=女真)」を撃退した英雄・藤原隆家の生涯をフィクションも交えながら描いた物語。2部構成で、第一部「龍虎闘乱篇」では藤原道長や花山院と争った若き日の隆家、第二部「風雲波濤篇」では壮年となり大宰権帥として刀伊と死闘を繰り広げる隆家の姿が描かれます。この作品の最大の特色は、隆家と刀伊の間にある“因縁”を設定したこと…歴史小説に“創作”を求めない方は引いてしまうかもしれませんが、“小説”として楽しむならば抜群に面白いですね!2025/03/01
新地学@児童書病発動中
138
気骨ある人物として歴史に名を残す藤原隆家の生涯を描く作品。非常に面白くて、400ページを超える長編を一気に読んだ。胸の内に荒ぶるものを秘めた隆家の人物描写が素晴らしい。「強い敵はおらぬか」とうそぶく若い隆家が、人生の浮き沈みを経て、権力争いの空しさに気づき、(わしは美しきものを守るために戦うのだ)と悟る場面には胸が震えた。清少納言や藤原道長、紫式部といった実在の人物が生き生きと描かれているのが嬉しい。隆家と渤海国の女性瑠璃のロマンスにより物語のスケールが雄大になっている点も気に入った。2015/10/11
たま
67
今年の大河ドラマに藤原隆家が出ると言うので読みました。第一部は花山院と藤原伊周・隆家兄弟の乱闘で兄弟は流罪になる。花山院の周りには渤海国末裔で女真族(刀伊)の烏烈や瑠璃がいて妖気を漂わせ伝奇小説の趣。第二部は隆家が太宰府で刀伊の船団を迎え撃つ。平安末期とは異なりこの頃は上流貴族にも武闘派がいたのだ。武士の起源に興味を惹かれる。彼らの武功に対し、文化人藤原公任は文書主義の屁理屈で恩賞を拒もうとしたとか。紫式部も短いが登場し父為時に伴い越前で宋人らと交流したと語る。これからドラマでどう描かれるか楽しみです。2024/03/29
財布にジャック
50
平安時代のあたりは苦手なので、かえって何も分からずに読んだので、新鮮に感じました。藤原家のゴタゴタと刀伊入寇の様子が丁寧に描かれていました。これを読む前までは刀伊が何なのかも知りませんでしたが、女真族のことだったのですね。隆家の闘う姿は格好良かったです。また、紫式部や清少納言の登場も花を添えてくれていました。2014/09/07
-

- 和書
- 異世界ドロンジョの野望
-

- 洋書電子書籍
- Students as Real Pe…