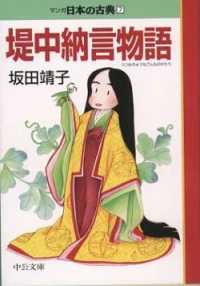内容説明
子どもたちの心の闇が「絵」に表れ出した。「人の記号化」「破壊性・攻撃性の噴出」「現実感の喪失」「存在感のない家」彼らを一刻も早く救出するために、大人たちは何をすべきなのか!?このままでは、子どもたちの犯罪も親による虐待もなくならない。
目次
プロローグ 私の子育て奮闘記
第1章 描画テストに表れた子どもたちの心の闇
第2章 少年の事件と犯罪を準備してきた日本の社会
第3章 現在の問題はすべて、1960年から始まった
第4章 “夫婦分業”から“夫婦協業”へ
第5章 これからの子育てをめぐって
著者等紹介
三沢直子[ミサワナオコ]
1951年生まれ。早稲田大学大学院心理学博士課程修了。明治大学教授。心理カウンセラーとして精神病院、神経科クリニック、病院の神経科などで、心理療法や心理検査に携わる一方、母親相談や母親講座などの子育て支援活動を行なってきた。コミュニティ・ワーカー養成のためコミュニティ・カウンセリング・センターを主宰。S‐HTP描画テストによる子どもたちの心理分析では定評がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
22
心理学の描画テストの経年比較をもとに、本来なら年齢の発達とともに写実的な絵を描くようになるのが、「思ったように描く」という観念的な絵を描く子どもが増えたことをもって、子どもの心理的成長が止まっていることを警告している。観念画とは、例えば人を記号のように描いてしまうような絵のことである。人物も風景も写実的に描けないのは、ゲームの影響や早期教育の影響があるという。少子化の時代にあって早期教育で成果を求められる子どもが多様で豊かな人間関係を育めていないことが成長を妨げる要因になるという。面白かった。2024/01/30
gatta blu
0
☆☆☆2016/07/20
omichio
0
まとめて読んだ中で一番よかった。プロローグにある著者の子育てに激しく共感。「肝っ玉母さん」にはなれない私、だけでも立ち読みしてほしい。自分に合う合わないは別にして読んでみてほしい本。副題にある「男性社会」をそれほど批判してはおらず、納得納得の話多し。2013/03/15
cochon_voyage
0
で、なぜ〈9〉歳?2021/05/16
まいちょろ
0
近年の子どもの心の成長EQが停滞しがちな理由を、家族、それを支える社会の観点から紐解いた本。自分の子育てを振り返ってみたく、手にとった。 親を支える必要性として、NP(ノンパーフェクトペアレンツ)の活動もとりあげられていた。 この本が書かれてから15年。日本は変わったか? 子育てはしやすくはなってきているが、依然として問題は問題のまま。政府の力も感じられず。海外の政策や価値観の紹介は勉強になった。2020/10/09
-

- 和書
- もしもに備える安心ノート