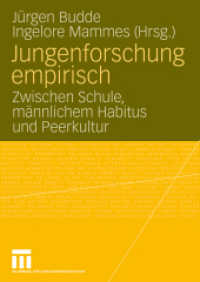目次
第1章 新学習指導要領の大きな変化(教育方法学研究からのアプローチ;総則の劇的変化と「育成すべき資質・能力」の徹底 ほか)
第2章 各論でつかむ改訂の特徴(幼稚園教育要領と小学校学習指導要領との連結;国語と算数などにみる基礎学力観 ほか)
第3章 学習指導要領をとりまく教育政策の背景(教育の歴史認識と二〇三〇年社会の描き方;中央教育審議会―諮問から答申へ至る過程の特質 ほか)
第4章 学習指導要領体制をのりこえる教育実践の方向(若い教師たちの苦悩と挑戦の姿;子どもと教育現場は、どうなりつつあるか ほか)
著者等紹介
梅原利夫[ウメハラトシオ]
和光大学教授。専門は教育課程論、教育方法学。1947年東京都生まれ。1972年東京大学教育学部卒業。1979年東京都立大学大学院博士課程単位取得退学。民主教育研究所代表、教育科学研究会常任委員、日本生活教育連盟会員、日本教育法学会常務理事、日本教育学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
33
新学習指導要領のもつ意味と政治的背景を学ぶことができました。道徳が教科化され、子どもたちの心の中にまで国家介入をしようとしているなかで、学習指導要領が現場に持ち込まれることによって教育する側の主体性や子どもたちの主体的学びが大きく侵害されるのだと思います。また今回の改定が第一次安倍内閣での教育基本法改悪を実行するものだということもわかりました。こうした教育が押し付けられているなかで子どもたちのための学校や学びをどのようにつくっていくのか、大人たちは深く考えなければならないと思います。2018/07/04
鵜殿篤
0
【要約】新学習指導要領は、あらゆる面に渡っておかしいところばかりです。無理です。 上から押しつけたアクティブ・ラーニングは、単に実践を形式的で無味乾燥なものに貶めるだけです。カリキュラム・マネジメントは、無理矛盾を現場に押しつけてきただけです。 子どもたちが主体となる教育に変えるためには、教師の自律性を取り戻すことが不可欠であり、そのために学習指導要領の法的拘束性はなくすべきです。教師の主体性が侵害されているのに、子どもの主体性を育てるなんて、無理です。2019/01/16