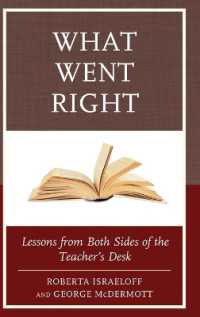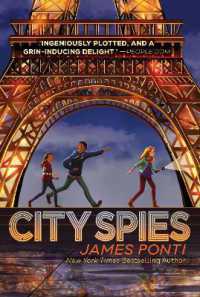目次
1 彼らのこと(難民とは誰か;難民ハイムの住民たち;彼・彼女らを取り巻く環境、ドイツ編―「やればできる!」)
2 十人十色の「難民と生きる」(マルティナ;アウグストとペーター;カティア;アマイ;クリストフ;ワルスラ;スザンナ;バーバラ;オブレイとサーラ)
著者等紹介
長坂道子[ナガサカミチコ]
1961年愛知県生まれ。ジャーナリスト、エッセイスト、作家。京都大学文学部哲学科卒業後、雑誌『25ans』(婦人画報社=現ハースト婦人画報社)の編集部を経て88年渡仏。その後、ペンシルヴァニア、ロンドン、チューリッヒ、ジュネーブなどに移住(現在はチューリッヒ在住)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yyrn
24
息子の小学校のPTA役員を引き受けた時から町内会活動に関わり早20数年。将来の町内会長候補だが(笑)家庭や会社以外のコミュニティ活動として半分は楽しんでやっているところがあり、マメに動いていると区や市の役員もお願いされるが、区や市レベルの活動はあまり身が入らない。▼この本ではドイツでの大量難民の受け入れに市民らが熱心に取り組んでいる状況がたくさんのインタビューから教えられるが、その献身ぶりには正直驚く。自宅に見ず知らずの難民を受け入れるなど多くの日本人にはできない相談だろう。ドイツでも排斥運動はあり、⇒2021/02/10
ののまる
16
ドイツで難民を家に受け入れた一般人などの生のインタビュー。普通のこととして、困っている人を支援する社会の成熟さ。2017/03/31
j
8
生まれる国は選択できないし、難民になる運命なんて誰にもわからない。難民キャンプに物理的支援をするだけでは、蚊帳の外で生活している私達の自己満足で終わっていて、根本的な難民問題の解決にはなっていないのかも...。そんな中、「まずは難民の人たちを受け入れることから始めよう」と自分たちの国に迎える若い人からお年寄りの人が大勢いて、困った人を助けるのが当たり前だと考えるドイツは慈愛に満ちた国だと思う。2019/01/17
makimakimasa
6
2015年に欧州30ヶ国は難民申請者130万人を受入れ、うちドイツだけで89万人(国民の11%=900万人が難民支援に関与、一方で同年の日本は申請7586人に対し認定27人)。無駄骨のたらい回しに遭っても、大河の一滴という無力感に襲われても、ハグや握手を巡る文化的習慣で揉めても、難民支援を通じて多くを学び自分も豊かになる―「世界旅行してるみたい」「一挙に全てを解決するビッグステップはそもそも無理」「ありがとうはお互い様」。人間の生き方や相互理解についてとても大事な事が書いてあり、多くの人にお薦めしたい本。2020/02/13
愛希穂
0
ドイツで難民の支援をしている人々を取材し、そのうちの10人の話を取り上げています。 難民の支援に消極的な日本ですが、こういう本が広く読まれて欲しいと思います。 それにしても、この違いはどこから来るのか。それについても示唆されていて、とても考えさせられる一冊。 [private]「自活できない貧しい人々を政府(国)が助けるべきである」 ・非常に賛成:イギリス-53%、スウェーデ…(ブクレコからインポート、全文はコメントに掲載されています)2017/05/26