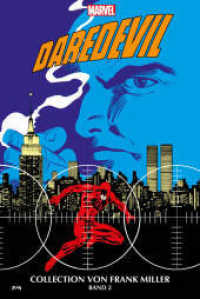内容説明
問われているのは“民主主義”と“私たちの社会”「しばき隊」創設時からカウンター運動を実践する法律家が徹底した現場目線でヘイト・スピーチ現象を解剖する!野間易通氏ほかカウンター市民へのインタビュー収録。
目次
第1章 2013年、新大久保にて
第2章 ヘイト・スピーチの深層にあるもの
第3章 ヘイト・スピーチは法で規制できるか
第4章 ヘイト・スピーチ規制をめぐる近時の情勢と私たちのとるべき態度
第5章 最後は市民の力
第6章 人びとの良心の輪に未来を託して
著者等紹介
神原元[カンバラハジメ]
1967年神奈川県生まれ。2000年弁護士登録。自由法曹団常任幹事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
SK
3
45*カウンター活動のルポが、とても良い。政治家によるヘイト。ヘイト・スピーチの法規制については、弊害も考慮しつつ、一定の効果はあるという立場。安倍政権のもとでの法整備は、反原発デモなど、政府にとって都合の悪いものまで規制されうる懸念もある。ヘイトは現行法では対処しきれない。各国の規制状況などについても参考になる。ヘイト・スピーチは、表現などではない。マイノリティを沈黙させ、社会、人間を壊す。映画についての話題が時折出てくるので、お好きなのかな?2019/02/10
Takuo Iwamaru
2
いかなる時も、想像力が大事だと思う。それは「相手が何を考えているか」を考えるということ。自分と反対の立場、理解できない立場の相手でも、想像力を巡らし、「相手が何を考えているか」を考えることで、見えてくるものがある。おぞましいヘイト・スピーチをまき散らし、本書が批判・攻撃の対象としている「在特会」についても―きつい努力を要するが―想像力を巡らすしかないのだろう。だが、学校や子どもをなぶる在特会の事例は、許せない。学校や子どもに向け、どのような心持ちで悪言を垂れ流したのか、それも想像してみるべきなのだろうか。2014/12/24
お魚くわえたザサエさん
2
違法とすべきヘイトスピーチの範囲として、マイノリティに対するものに限定すべきとあるが、その根拠が示されていないように思う。どのくらいの数の集団をマイノリティとするかとか、マイノリティではあるが強者である者が、マジョリティではあるが弱者である者に対し差別的な発言をすることはどうなのか。もちろん、何を根拠として強者弱者の定義を決める必要がある。2014/12/30
たろーたん
1
興味深かったのが、ヘイトスピーチに対する外国での立法例。ドイツの民衆扇動罪は被害者の範囲が「住民の一部」とだけ規定しているため広いのが問題で、ユダヤ人やカトリック、難民等以外にも留学生、労働者、公務員、裁判官、警察官、軍隊なども入ってしまうらしい。そのため、1991年湾岸戦争時に「兵士は人殺しだ」と書いた平和活動化が起訴されたようだ。「ドイツ連邦軍兵士は人殺しだ」ではなかったため無罪となったが若干疑問が残る。(続)2025/08/10
樋口佳之
1
50代以上の方に是非読んで欲しい本。ヘイトスピーチに留まらない示唆を得る本です。