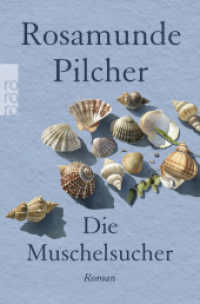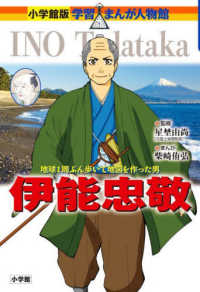内容説明
美しい川や湿地を保全し、多彩な生きものがすむ自然豊かな水辺をどう復元するのか―すみ場の階層構造の理論を活かした新しい試みや国内外のとりくみを多数の写真とともに紹介し、治水・利水と生態系の保全、住民の主体的な参加による環境民主主義のあり方を考える。待望のシリーズ第四冊。
目次
1 新しい視点を(土木と生態が共働するテーブル;「脱ダム宣言」;川の環境民主主義 ほか)
2 新しい仕事(水循環の保全;スイゼンジノリと水循環;グライフェン湖の湿地再生 ほか)
3 水辺あれこれ(千曲川の植生回顧;霞ケ浦の植生回顧;ワンドとタマリ ほか)
著者等紹介
桜井善雄[サクライヨシオ]
1928年長野県生まれ。1948年上田繊維専門学校(現:信州大学繊維学部)卒業。1948~1994年上田繊維専門学校・信州大学繊維学部に46年間勤務、応用生態学講座を担当。農学博士。1994年信州大学を定年退官。信州大学名誉教授。応用生態学研究所(私設)を開設主宰。1994年から国内および国外において、自然環境、特に湖や川の水辺の自然環境保全の理論と方法について調査・研究を行い、国および地方自治体の委員会や懇談会、および市民団体等との交流を通してその成果を実際に生かす活動にとりくんでいる。月刊誌『水』に毎月学術エッセイ「水の風景」を連載(現在174回)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。