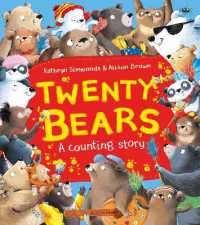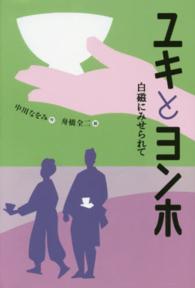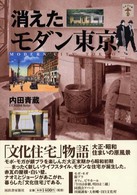内容説明
若い女性が毎日一六時間働き、夜は劣悪な寄宿舎生活。製糸工女が主要な労働力だった日本の殖産興業政策。製糸業の技術と労働の実際を、繊維技術者の体験をふまえて克明に綴る。
目次
製糸工女の一生
製糸工女の仕事
蚕病から始まった日本の蚕糸業
官営富岡製糸場から始まった工場制度
「罰がこわい」繰糸工女の出来高賃金
繰糸工女の出来高賃金制の本質
製糸工女は毎日一六時間働いた
工女の出身地、年齢、勤続年数
シラミが嫌だった寄宿舎のくらし
工女と結核
おくれた日本の工場法
養蚕農民のくらし
蚕糸業を支えた行政・教育
大恐慌と工女たちのたたかい
著者等紹介
玉川寛治[タマガワカンジ]
1934年長野県松本市に生まれる。東京農工大学繊維学部繊維工学科卒業。産業考古学会理事・編集部会長。日本産業技術史学会会員。東京国際大学非常勤講師。元大東紡織(株)技術者
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みか
9
手にとってそのずっしりとした重さに先ずびっくり。製糸工場の女工の生活が知りたくて読んでみました。具体的な記述が多く、主要なテーマごとに章分けしてあるので、逆引きもしやすそう。データも多く、とても参考になりました。基本、諏訪の製糸場が中心なので、それもポイント高かったです。勉強になりました。もっとこういう本が有ればいいのになぁ。 2015/01/01
Olive
8
玉川氏は40年間繊維技術者として働いてきた。ご自身の義母も13歳の時から製糸工女として働いた聞き取りもある。 富国強兵時代の製糸業と綿紡績業を俯瞰する。特に繊維技術に関しての記述が専門的だ。技術がどのように育成され、保護され、技術革新がおこなわれたのかを技術面、工女からみた労働、国家政策などから多角的に書かれている。女性の仕事として、工場労働者として、日本で工場法がどのような経緯を辿り成立にいたったのか、現在の基本的人権の一つである労働三権がこのような経緯でできたのかもわかり腑に落ちた。勉強になった。2022/07/10