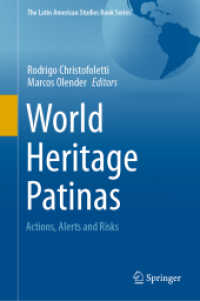出版社内容情報
葬儀までの手続きは、だいたい葬儀屋さんにお任せできます。
でも、その後の手続きや届け出は自分でしなければなりません。
じつは、これらの手続きには、結構いろいろなものがあり、手間がかかります。
相続の手続きはもちろんのこと、亡くなられた方の確定申告も、代わりにしなければなりません。
また、健康保険や年金の手続きもあります。
亡くなられた方が持ち家をお持ちなら、世帯主の変更手続きが必要なケースもありますし、光熱費の支払先の変更やNHKの受信料の手続きなども必要です。
これらの中には、手続きや届け出をしなければ、損をしてしまうものが少なくありません。反対に、手続きや届け出をすることで、得するケースもあります。
本書はこれらの手続きや届け出の仕方を、記入例とともに、ていねいに解説しています。
また、これらの手続きをするために必要な書類を、役所などから入手しなければなりません。本書では、これらの入手方法にも触れています。
これらは一般に、税理士、司法書士、社会保険労務士など、何名かのプロに相談しなければなりません。
本書は監修者に、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士の資格を持つ方をむかえています。
懇意にしている税理士や司法書などの専門家がいらっしゃるのでしたら、これらの手続きは彼らにお任せできます。
でも、そのような方々が周囲にいらっしゃらないのでしたら、本書はとても役立つ一冊になります。
※本書は2019年刊行の『新版 大切な家族がなった後の手続き・届け出がすべてわかる本』を最新の法律や手続きに沿って新しくしたものです。
内容説明
必ず“しなければならない”手続きを、すべて自分でできます!健康保険、年金、葬祭費、死亡一時金、遺言の検認、遺産分割協議書、相続税、銀行口座、自動車…など。2022年3月最新の法律・書式に対応!
目次
第1章 すぐにしなければいけない手続き―翌日から2週間くらいの間に行なう手続きはこれだけです
第2章 少し落ち着いたら最初に確認したいこと―次の手続きを始める前にこれだけ知っておきましょう
第3章 できれば早くしておきたい手続き―急ぐ手続きを済ませたら、3~4カ月くらいをめどに進めましょう
第4章 健康保険と年金で必要な手続き―期限の余裕はありますが、順番に済ませていきましょう
第5章 遺言と遺産分割の手続き―後の手続きのためにも早めに着手しましょう
第6章 遺産の相続と名義変更の手続き―遺産ごとに相続届や名義変更の手続きが必要です
第7章 相続税の申告と納税の手続き―10カ月以内に納税まで済ませる予定を組みましょう
著者等紹介
関根俊輔[セキネシュンスケ]
税理士。中央大学法学部法律学科卒。平成19年税理士登録、税理士法人ゼニックス・コンサルティング社員税理士。近年の高齢化に伴い、「亡くなる前」の贈与や相続税の事前対策から、「亡くなった後」の遺産分割、二次相続に至るまで、財産の収益化・コンパクト化を重視した、遺族の暮らしの総合コンサルティングを提供している
関根圭一[セキネケイイチ]
社会保険労務士、行政書士。30年を超えるキャリアの中、遺言書の作成、立ち会い、健康保険の切り替え、遺族年金の請求等、数百名分の実務に対応した実績を持つ。大切な家族が亡くなることは、常に稀であるという考えのもと、難しい手続きをわかりやすく説明し、故人の代わりとなって、遺族との円満な遺志疎通を実現している
大曽根佑一[オオソネユウイチ]
司法書士、行政書士。中央大学法学部法律学科卒。平成17年司法書士登録、平成26年行政書士登録。司法書士・行政書士大曽根佑一事務所代表。街の法律家として、相続発生以前の遺言書等による紛争予防アドバイスから、相続発生後の登記手続・相続財産管理業務に至るまで、相続にまつわる多岐の分野に積極的に取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 洋書
- Cartacei