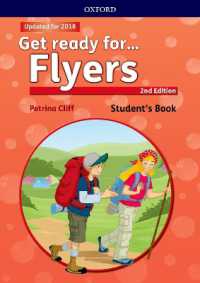内容説明
戦中戦後を通して日本人の心の中に生き続けた「海軍兵学校」―その素顔を歴史を、貴重な写真資料と多角的な検証・論考によって描き出す。兵学校に在校した旧海軍将校、そして戦後海上自衛隊幹部学校での教育に携わった方々の随想も掲載。
目次
写真でたどる江田島海軍兵学校写真帖(海軍兵学校生徒の素顔―眞継不二夫氏写真より;今日の兵学校海上自衛隊幹部候補生学校―眞継美沙氏写真より ほか)
教育参考館ガイド(海軍兵学校の宝物)
知っておきたい海軍兵学校の基礎知識(江田島海軍兵学校通史;近代史の中の海軍兵学校)
人と思いがつなぐ伝統海軍兵学校随想(江田島を憶う;江田島と海上自衛隊幹部 ほか)
そこが知りたい論考 海軍兵学校(セシル・ブロックの観察とその今日的意義;戦後の江田島復興と再生 ほか)
著者等紹介
平間洋一[ヒラマヨウイチ]
昭和8年(1933)横須賀生まれ。1957年、防衛大学校本科(電気工学専攻)卒(1期)。在校事、英語会話部創立に尽力。1957年、海上自衛隊に入隊、1958年に3等海尉任官、同幹部学校指揮幕僚課程、護衛艦「ちとせ」艦長、統合幕僚学校教官、第31護衛隊司令、呉地方総監部防衛部長、防衛研究所戦史部研究員などを経て、1998年、退職。同年より防衛大学校講師、教授を経て1999年退官。筑波大学、常盤大学、大阪大学の非常勤講師を歴任。現在は軍事史学会理事、太平洋学会理事、戦略研究学会理事、呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)委員、横須賀市史編纂委員、特定非営利活動法人岡崎研究所理事、社会福祉法人興寿会理事などを務める
市来俊男[イチキトシオ]
大正8年(1919)鹿児島県生まれ。元海軍大尉。昭和10年(1935)、海軍兵学校入学。昭和15年に少尉に任官。昭和16年の開戦時には中尉。駆逐艦「陽炎」航海長。同18年には重巡「青葉」、戦艦「山城」の分隊長を勤めたあと、海軍兵学校教官となる。終戦後、海防艦「生名」艦長となり、機雷掃海に従事したのち復員。同27年、海上警備隊に入隊し、自衛艦隊、海上幕僚監部、幹部学校、防衛研究所などに勤務。昭和47年の退官後は防衛研究所戦史室戦史編纂官、戦史研究室長などを勤める。現在は前の大戦の研究と執筆を続けている
雨倉孝之[アメクラタカユキ]
昭和3年(1928)東京生まれ。同20年(1954)4月、高等商船学校東京分校(機関科)に入校、あわせて海軍機関術予備練習生を命ぜられる。終戦により同年8月、退校、同時に予備練習生も被免。戦後、日本国有鉄道に勤務。59年(1984)、退職。東京理科大学理学部卒業の技術屋出身だが、かねてより海軍史・海事史の調査にたずさわり、現在、特に海軍制度史の研究に取り組んでいる
影山好一郎[カゲヤマコウイチロウ]
1942年、大阪生まれ。昭和40年(1965)防衛大学校本科を卒業し、海上自衛隊入隊。防衛大学校研究科卒業。海上幕僚監部防衛課。昭和60年、防衛大学校教授(海軍戦略)となる。東郷幕僚会議事務局、第二航空群支援整備隊司令を経て、1997年、防衛大学校教授(軍事史・海軍史)。2007年退職
北澤法隆[キタザワノリタカ]
昭和13年(1938)生まれ。海上保安大学校卒。海上自衛隊入隊。「きたかみ」航海長、「しきなみ」「とかち」「むらさめ」各砲術長を歴任。元防衛研究所戦史部主任研究官。史実と艦艇勤務経験からの視点で、海軍史・海戦史を研究。神奈川県横須賀市在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てつのすけ
かおりんご
ケケ内