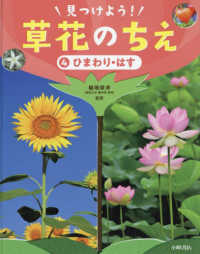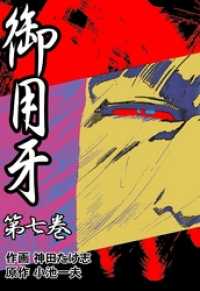内容説明
名族・橘氏はたったひとりの女から始まった!天武・持統・文武・元明・元正・聖武―六代の天皇に仕え、後宮を束ねて皇位継承に絶大な影響力を持った橘三千代。美努王の妻から藤原不比等のもとへ―激しくしたたかに生きた波瀾の一生を鮮烈に描く雄渾の歴史巨篇。
著者等紹介
梓沢要[アズサワカナメ]
本名・永田道子。昭和28年、静岡県に生まれる。明治大学文学部史学地理学科卒業。平成6年、『喜娘(きじょう)』で第18回歴史文学賞受賞。著書に『阿修羅』『喜娘』『百枚の定家』『遊部』等がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keith
16
「四神の旗」の予習。不比等というフィクサーがいたものの、この頃は三千代、持統天皇、元明天皇、元正天皇、光明子といった女性たちが歴史を動かしていたことが分かります。この本では不比等の息子たち藤原四兄弟も一枚岩ではないようですが、実際のところはどうだったんでしょう。2020/06/13
take5
9
下巻では文武即位式から三千代の死後までが、基本続紀の記事に沿って描かれます。著者独自の想像と思われる面白かった点は、藤原宮子の首皇子(聖武)の出産場面(難産。迫力あり)、「橘」という姓の由来(生地近くの餌香の市 (えがのいち)に関連)、後宮官員令の作成に三千代が関与するところ、安宿媛が書記編纂に利用されたともされる『善言』で帝王学を学んだところ、不比等の死に至る原因は三千代との娘の安宿媛と多比能の間の問題に起因したとするところ(年表的にも符合)、長屋王邸跡を光明皇后の皇后宮職などに利用した理由などでした。2024/09/07
モルク
5
もっとしたたかさと豪傑さを感じさせる女傑かと思ったが意外と普通のかんじだった。光明子もインパクトが薄い。もしかしたら、そんな感じだったのかも。2015/06/09
yonemy
4
藤原氏の繁栄の礎を築いた不比等の妻。内助の功はもちろん、自分自身も出世して、一族を引き上げる、まさに「やり手」な女性だ。夫唱婦随に立身出世、絵に描いたようなサクセスストーリーだが、皇位をめぐる血なまぐさい争いに渦中にい続けた三千代は、平穏な日々とは遠い。彼女を幸せとは、私には思えなかった。 2018/05/04
KIYO
4
とても面白く読み応えのある上下巻でした。天武天皇から聖武天皇まで5代の天皇近くに仕えた三千代の生涯を追えば、この時代の大きな流れは教科書よりもよくわかります。2017/01/11