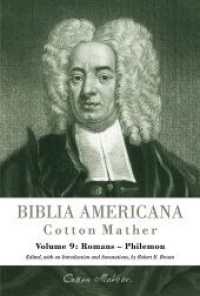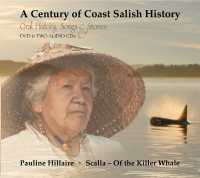内容説明
ナポレオンのエジプト遠征が聖書を現実の光景に変えた!サロメの誕生にオリエンタリズムの起源を探る、才媛の力作評論。フローベール『ヘロディア』、ワイルド『サロメ』の新訳を付す。
目次
聖書とオリエントの地政学(少女・淫婦・斬首;オリエントの地政学;幻想としてのサロメ)
ヘロディア
サロメ
著者等紹介
工藤庸子[クドウヨウコ]
1944年浦和生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。フランス近代小説の背後にある時代精神を明らかにするとともに、古典に新しい光を当てる清新な翻訳で知られる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コニコ@共楽
19
洗礼者ヨハネの最期を綴った福音書の話から派生した物語には、名前さえ書かれていなかったのが、どう今のサロメになっていったかが、興味深く解説されていた。フローベール『ヘロディア』とオスカー・ワイルド『サロメ』は、それぞれの時代の雰囲気を吸いながら、オリエンタルな話を劇的に魅力的に昇華していったと感じる。ユディトのイメージにもダブらせているサロメ像が心の中に浮かんできた。工藤氏の『ヘロディア』、『サロメ』の翻訳付き。2022/09/30
K
11
『サロメ』の背景を知るために軽く読む。19世紀という時代背景とサロメ誕生の関係が知れる。フロベールのオリエント遠征時の手記(pp.43-44)の彼の興奮ぶりが面白い。脱宗教化しつつも、古代オリエントの再発見そして、聖書に立ち戻るという図式は、なるほどと思った。若干の理解不足だが、深堀はまたの機会に譲る。『サロメ』『へロディア』の訳が付いているが、訳注が充実しているのが、非常に助かった。2023/05/26
ティス@考える豚
4
キリスト教理解に関して。文学・絵画・オペラ・宗教考の一つのモチーフとなる。オリエント、主にエジプトやシリア、パレスチナ、イスラエル等との関連。少しだけインドとの関連。フローベール、ワイルド、エルネスト・ルナン等、英仏文学者についての論考。キリスト聖書の一ジャンル。まだ理解が浅い。ワードとして、サロメ、ユディト、ヨカナンなど人物名が主。2013/01/27
スミレ雲
3
【図書館本】聖書読んだことないので、厳しかった。サロメがいろんな象徴となっていることは良く分かった。西洋的教養がベースにないと、なかなか読解難しい。2019/10/26
misui
2
フローベール『ヘロディア』、オスカー・ワイルド『サロメ』(両作品ともサロメのバリエーション)と論考を収録。十九世紀ヨーロッパ、脱宗教化運動によって、宗教を遠ざけるというよりむしろ冷静・科学的に宗教を捉える姿勢が生まれ、国民のアイデンティティを証する身近な宗教幻想、つまり聖書へと注目が集まった。その流れの中でオリエンタリズムとも合流し、サロメは一大ジャンルとして隆盛を誇ったという。ざっと目を通したけどサロメ自体は思ったより面白くなかったな…。2011/11/15