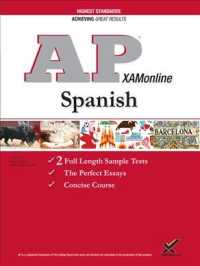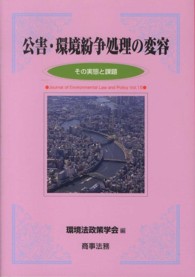内容説明
福音書に記されたイエスのたとえの中でも最もよく知られている“放蕩息子”。このたとえは古代以来数多くの人々のたましいに刺激を与え、様々な解釈と造形を生み出してきた。いま危機と混迷の時代を生きる私たちは、このたとえから何を読みとることができるのか。豊かな学殖と深い洞察をもって解釈史をたどりながら、神と人間のドラマを読み解く。
目次
第1部 キリスト教美術の中の“放蕩息子”(中世教会美術;宗教改革の時代の“放蕩息子”―デューラーとヒエロニムス・ボス;レンブラントの“放蕩息子”;ロダン以後バルラッハまで;現代美術の中の“放蕩息子”)
第2部 “放蕩息子”の精神史(“放蕩息子”のたとえを読む;“放蕩息子”の精神史―古代教会から宗教改革まで;近代文学の中の“放蕩息子”―ジイド・リルケ・カフカ;“放蕩息子”の精神分析学的解釈―自己実現と影;“放蕩息子”と現代文明―明日への希望)
著者等紹介
宮田光雄[ミヤタミツオ]
1928年、高知県に生まれる。東京大学法学部卒業。東北大学名誉教授。長年、学生聖書研究会を主宰して伝道に献身し、自宅内に学寮を建てて信仰に基づく共同生活を指導してきた。主な著書は『西ドイツの精神構造』(学士院賞)、『現代日本の民主主義』(吉野作造賞)(岩波書店)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
megumiahuru
8
元来、ドイツ政治思想史(特にナチスの時代)が専門の著者ですが、キリスト教に関する著作も多くあります。これもその一つ。聖書の「放蕩息子のたとえ」が、美術史や文学・思想史の文脈の中でどのように解釈され、影響を与えてきたのか、とても分かりやすく書かれています。改めてヨーロッパの文化にキリスト教が与えた影響の大きさを感じさせられます。こういう本を片手にヨーロッパを歩いてみたいと思わされました。2013/07/01
きゅーま
2
聖書にある<放蕩息子のたとえ>を、前半ではそれを題材に取られた絵画から絵画史を、後半ではそれがどう読み解かれていったのかの精神史をわかりやすく解説してくれています。導入として読みやすい本だと思います。2013/01/20