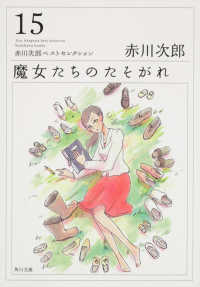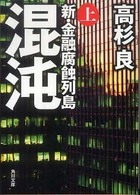内容説明
深川の茂平は大工の棟梁を引いて隠居の身。生来の仕事好きには、ひまでひまで仕方ない。そんな茂平、いつの頃からか「ほら吹き茂平」と呼ばれるようになっていた。別に人を騙そうとは思っていない。世間話のついでに、ちょっとお愛想のつもりで言った話がしばしば近所の女房たちを、ときには世話好き女房のお春までをも驚かす。その日は、一向に嫁がない娘を連れて相談にきた母親に、いつもの悪戯ごころが頭をもたげてきて…。(「ほら吹き茂平」より)。やっかいな癖、おかしな癖、はた迷惑な癖…いろんな癖をもった人がいるけれどうれしいときには一緒に笑い、悲しいときには一緒に涙する。江戸の人情を鮮やかに描いた時代傑作。
著者等紹介
宇江佐真理[ウエザマリ]
北海道函館市生まれ。1995年、「幻の声」で第七十五回オール讀物新人賞を受賞しデビュー。2000年に『深川恋物語』で第二十一回吉川英治文学新人賞を、翌01年に『余寒の雪』で第七回中山義秀文学賞を受賞。以後、江戸の市井人情を細やかに描いて人気を博す(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





ミスランディア本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shinji Hyodo
86
大工の棟梁である茂平の話が綴られる連作短編集かと思いきや、一編読み切りの六遍の短編集だった。そんな中で、二編目「千寿庵つれづれ」と五編目「妻恋村から」が連作で、主人公の尼僧の不思議な力が描かれたファンタジー。「親の意見となすびの花は千にひとつの無駄もない」我が家の坊主様がこの手の格言⁉︎に気付いてくれる日が来るだろうか?無理だろうな…私自身がそんな親の意見や叱言に気付かずにこの歳になっちまったんだものなぁ(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)2017/11/01
baba
43
6年振りの再読、すっかり忘れている。宇江佐さんの市井ものとは一風変わった短編集。表題作は生きることが辛い時ほらを吹いて楽しく過ごすすべを覚え、女房を何より大事に思う茂平はなかなか魅力的です。「千寿庵つれづれ」と「嬬恋村から」は連作で亡くなった人を感じる庵主が生きる事を大切に思わせてくれる、珍しいファンタジー風の話し。2016/07/24
さなごん
30
短編集だった。幽霊の見える尼さんの話がおもしろかった。他もしみじみじんわり。金棒引きの話はよくわからず。2015/12/28
Makoto Yamamoto
27
再読。暖か味のある「ほら吹き茂兵衛」はじめ、江戸庶民が題材の時代小説短編集。 千寿庵の尼僧関連の「千寿庵つれづれ」、「妻恋村から」は当時の家族の役割を踏んでの話で、辛いところを尼僧のおかげで明るくなるいい話。 いつ読んでも宇江佐ワールドはいい。2021/10/14
トラキチ
27
初出「小説NON」。サブタイトルの“なくて七癖あって四十八癖”が示す通り個性的な人を描いた短編集。テイスト的には藤沢周平の『たそがれ清兵衛』の市井物版だといったらよいのでしょうか。 たとえ武家物を描けば偉大なる先輩の藤沢氏に劣るかもしれませんが、市井物では藤沢氏の端正な文章には見劣りはしても、しみじみとした内容では引けをとらないと感じられます。 決して泣けるような話じゃないんだけど、適度にほろっとさせてくれます。このあたり他作との兼ね合いを考えて宇江佐さんのレベルでは書き分け出来そうな気がします。→続く2013/09/28
-
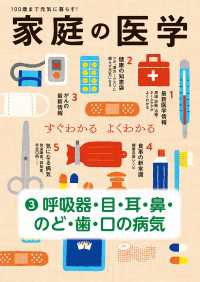
- 電子書籍
- 家庭の医学 電子分冊版(3)呼吸器・目…
-

- 電子書籍
- まるわかり! 人工知能 最前線 2018