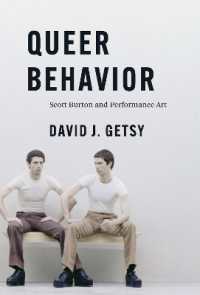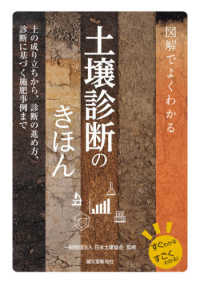出版社内容情報
考えるヒントを求める人へ
人間と社会を深い洞察で解き明かしてきた著者が、
パリ第八大学でフランスの学生に説いてきた
知のあり方、方法論。
創造を称揚する貧困な常識を捨て、
もう一度考え直そう。
なぜ学ぶのか、なぜ知りたいのか。
* * *
矛盾の解き方を先達からどう学び、どう活用するか
文献収集や調査の方法、論文の書き方、
斬新なテーマを見つけるコツなどの技術やノウハウの前に
学ぶべき、もっと根本的なことがある。
『社会心理学講義』も方法論だったが、
本書は社会科学全般に視野を広げるとともに矛盾の一般的解法に焦点を絞った。
多様な分野の知見を一緒にした時、隠れていた矛盾が露呈する。
見過ごしてきた問いに気づく。
その際に型が果たす役割の分析が本書の仕事である。
――「はじめに」より
* * *
[目次]
第一章 創造性という偽問題
第二章 矛盾を解く型 同一性と変化をめぐって
第三章 主体虚構論の舞台裏
第四章 モスコヴィッシの贈り物
第五章 躊躇と覚醒
第六章 社会は制御可能か
終章 残された仕事
内容説明
考えるヒントを求める人へ。人間と社会を深い洞察で解き明かしてきた著者が、パリ第八大学でフランスの学生に説いてきた知のあり方、方法論。
目次
第1章 創造性という偽問題
第2章 矛盾を解く型 同一性と変化をめぐって
第3章 主体虚構論の舞台裏
第4章 モスコヴィッシの贈り物
第5章 躊躇と覚醒
第6章 社会は制御可能か
終章 残された仕事
著者等紹介
小坂井敏晶[コザカイトシアキ]
1956年愛知県生まれ。アルジェリアでの日仏技術通訳を経て、1981年フランスに移住。早稲田大学中退。1994年パリ社会科学高等研究院修了、リール大学准教授の後、パリ第八大学心理学部准教授。2022年退官(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
まこみや
hasegawa noboru
Hiro
おやぶたんぐ
-
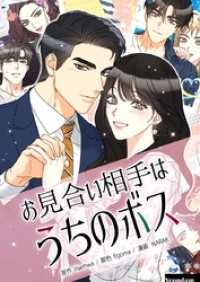
- 電子書籍
- お見合い相手はうちのボス【タテヨミ】第…
-

- 電子書籍
- 男をやめてみた~癌になったので女装して…