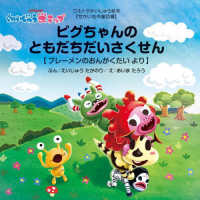- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
もしも五重塔や本堂の「軒(のき)の線」が真っ直ぐな直線だったとしたら、はたしてそれらの建物に美しさをお感じになるでしょうか。伝統的な日本の社寺(しゃじ)建築の美しさの根源は、端(はし)に近づくにしたがって緩(ゆる)やかに反(そ)っていく、華麗な「軒反り(のきぞり)」にあります。そして、昔の大工の知恵と技術が一番詰まっているのも「軒反り」なんです。コンクリートや鉄骨であれば、どんな曲線を作るのも自由自在でしょうが、木を組んで美しい曲線、「軒の反り」を出すにはとても高度な技術が必要になります。(まえがきより)――文化財専門の"最後の宮大工"が語る、日本の伝統技術の素晴らしさ。(祥伝社販売課大胡田オススメの一冊)(祥伝社販売課石原オススメの一冊)語りつがれる英知と伝統。後世まで末永く伝えたいものです。
文化財専門の最後の宮大工と言われる筆者が、全国各地の国宝や重要文化財建造物の修理工事から得た昔の宮大工の建築術について、概説した好書である。
●知識の様々なかたち
知識にはどのような種類があるのか。言表可能な、理論化された知識をはるかに超えた、広大な知識のスペクトラムを紹介し、知識科学がとらえようとする対象の複雑さと豊かさを明らかにする。
知識とは何か。どのような種類があるのか。いかに表現されるのか。いかに伝達されるのか。
人工知能、認知科学、脳科学の成果を結集しても、こうした疑問に対する最終的な答えはまだ出ていない。知識とそれを取り巻く現象の体系的な理論はまだ存在しない。だから、単なるキーワードとして、一時のはやり言葉として、「知識」を終わらせないために、知識のあるゆる実践の分析と、そのメカニズムの体系的理解が要求されている。
内容説明
「木を生かす」という、昔の大工の知恵を今の日本人に伝える。
目次
1章 雀と大工は軒で泣く―鎌倉・室町に花開いた、日本的「美」の曲線(五重塔―美しさの秘密;日本的「美」に、いかに「軒反り」が重要か ほか)
2章 木造建築に秘められた日本人の英知―なぜ古建築は千年の命を持ちえたのか(ヒノキだけではない、古建築の素晴らしさ;礎石と柱―湿気を逃がす工夫 ほか)
3章 「木の文化」は、なぜ衰えつつあるのか―文化財を守る修理、壊す修理(「木を生かす」ための、さまざまな知恵;ずぼらな仕事が横行するようになった理由 ほか)
4章 旅回りの「渡り棟梁」―古き良き“職人の世界”(私の原点―平等院鳳凰堂;紀三井寺で出会った恩師から学んだこと ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マッピー
NOYUKI
subabai
方々亭
林芳
-

- 電子書籍
- 建設施工