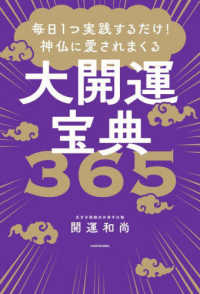内容説明
人間誰しも、嫉妬からは逃れられない。松下幸之助が「嫉妬心は狐色に程よく妬かなければならない」と述べたように、その存在を認めていかに飼い馴らすか、そして他人からの嫉妬をどのように避けるかが肝要である。歴史上の人物から現代各界まで豊富な事例を紹介し、日本社会で生き抜く術を説いた名著、ここに復刊。
目次
第1章 嫉妬の正体
第2章 嫉妬と私
第3章 嫉妬とアカデミズム
第4章 嫉妬と有名人
第5章 嫉妬の日本史
第6章 嫉妬と宗教
第7章 嫉妬の形態学
第8章 男の嫉妬・女の嫉妬
第9章 嫉妬の効用
著者等紹介
谷沢永一[タニザワエイイチ]
1929年、大阪市生まれ。関西大学文学部国文学科卒業、同大学院博士課程修了、文学博士。関西大学文学部教授を経て、名誉教授。専門は書誌学、日本近代文学。著書に『完本 紙つぶて』(サントリー学芸賞)、『文豪たちの大喧嘩―〓外・逍遥・樗牛』(読売文学賞)、『紙つぶて 自作自注最終版』(毎日書評賞)など。2011年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
95
谷沢さんがこのような本を書いていたことを初めて知りました。数多い御本を読んでいるからこそ様々な嫉妬の形態を紹介してくれているのではないかと思います。最初に松下幸之助翁の言葉がありこの嫉妬がないと社会は進歩を遂げないのではといわれていて、最後にも嫉妬の効用があり参考になりました。2021/06/24
すうさん
7
面白く読んだが、事実なのだか小説の中の話なのか混合して不思議な論調である。嫉妬に関しては人間の感情の中では最も強いもので、日本人の歴史はほとんどそれに裏打ちされているという論評は行き過ぎだと思う。嫉妬とは複雑な感情ゆえの反行動だと思うが、全ての裏切りがそうだとは思えない。しかも嫉妬の感情を抑えるのは「謙虚であれ」などと簡単に一括していたのは笑えた。世界中の大きな事件を嫉妬が原因だと語るのに、その答えは簡単すぎる。嫉妬の正体は人間のもと複雑な感情(自分愛の裏返し)とその不合理な行動によるものじゃないかなあ。2021/03/19
うだうだ
6
嫉妬への対処がわかればと考え購入。脳科学が出てくる以前に人の感情に焦点をあてるとこうなるのか。嫉妬については、個人的には「人はいじめをやめられない」をおすすめしたい。アカデミズムのところは、嫉妬の濃さってこんなものかと思える。若かりしころ足を引っ張られたり、謎に貶められた気がするが、こんな人に近かったのかな?とか、そんなことが頭をよぎった。嫉妬と日本史では、歴史の出来事や人物像を司馬遼太郎氏の著作から引っ張ってきているが、小説を歴史的事実の根拠のように記すのは、エッセイ的読み物でもまずいのでは?と思った。2021/01/28
ふたば
5
人間は嫉妬から逃れられないのだという。それは、たとえ名を成した人物であったとしてもだ。内容的には、それは嫉妬、と言う感情ではないのでは。。?と思うケースもあったり、嫉妬とは関係のなさそうな話もあったりと、けっこう楽しみがら読めた。自分は、コンプレックスの強い人間であるから、どうしても他者との比較で、負の念を持つことも多い。嫉妬深い人間であるという事か。嫉妬に駆られてみっともない行動はしたくないが、嫉妬との感情は、上手く使えば自分を向上させる原動力ともなるようだ。上手く付き合っていきたいものだ。2020/12/26
ワンモアニードユー
4
松下幸之助の「嫉妬は程よく狐色に焼く」がどれほど深い言葉だろう。自身の嫉妬心に悩む心を少し救った。古い本だが、日本人の嫉妬の正体を実例を交えて喝破し、しかしそれを活かすにはどうすればよいかという、毒を薬とする手法も提示。いい本だが、2章程度余分だと思う。意図はあるのだろうが辟易する。2023/08/16
-

- 電子書籍
- イケメン社長に憑依されました【タテヨミ…
-
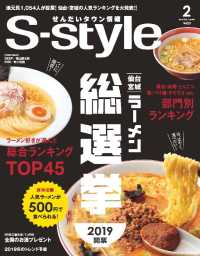
- 電子書籍
- せんだいタウン情報S-style - …