内容説明
一九四四年、何が行なわれたか。昭和十九(一九四四)年二月二十一日、東條英機首相兼陸相は参謀総長に就任する。明治維新以来、首相・陸相・参謀総長を一人で担った人物はいない。陸軍はもちろん、内務省などにも人脈を張り巡らせた、長州閥の領袖・山県有朋ですら、なし得なかった。各所から反発・抵抗を受けるなか、東條はなぜ権力集中を強行したのか。本当に独裁者なのか。著者は、近代日本の矛盾を体現したのが「一九四四年の東條英機」であり、そこから「明治のシステム」の欠陥が読み解けるという。昭和史に新たな視点を持ち込み、これまでの東條像に一石を投じる意欲作。
目次
はじめに―日本近代史における一九四四年
第1章 反長州閥の血 1855~1913年
第2章 栄達、そして開戦へ 1914~1943年
第3章 東條包囲網 1943年
第4章 集中する権力 1944年
第5章 崩壊 1944~1945年
終章 近代日本の限界
おわりに―スガモプリズンの痕跡
著者等紹介
岩井秀一郎[イワイシュウイチロウ]
歴史研究者。1986年、長野県生まれ。2011年、日本大学文理学部史学科卒業。以後、昭和史を中心とした歴史研究・調査を続けている。著書に、山本七平賞奨励賞を受賞した『多田駿伝―「日中和平」を模索し続けた陸軍大将の無念』などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nnpusnsn1945
54
7月7日は盧溝橋事件とサイパン島玉砕の日という事で積んでいた本書を読んだ。東条の父は才能はあったものの、藩閥によって出世を阻まれた経験があった。ゆえに英機は長州閥を憎んだ。真面目一辺倒で官僚としては優秀だが、藩閥が消滅した弊害として政軍関係がうまくゆかず、様々な職務を兼ねて失策が続いた。ガ島、インパール等(書かれてはいないが1号作戦)の責任も無いとは言えない。2021/07/07
活字の旅遊人
20
保阪正康「昭和の怪物 七つの謎」から、東條英機について学ぼうと手に取る。開戦から詳しく書かれ出すので、それ以前の背景などはもの足りず。昭和天皇への忠節心や己への厳しさ、几帳面さは、「七つの謎」以上に伝わった。また、陸軍と海軍とに統一した見解がないという事態に苦心していたことも理解できる。が、やはり一方の出身者が総理大臣という立場になってしまえば、他方からより反発を招く結果になるだろうことは、想像できる。自分のいる組織の視点にしか立てず、大局を見ることができない、というのは、残念な結果をもたらすものだ。 2020/12/22
駄目男
16
面白いじゃないか東條さん。これは良い本だったね。戦後、東條英機は一方的に断罪されてきたが、果たして事実はそんな単純なものだろうかと長らく思ってきたのだが。旧帝国憲法の狭間で悩み苦しむ、総理東條英機と言う人を冷静に俎上の上で解体していく処方に感動した。この問題を理解する上で欠かせない統帥権という、昭和陸軍を苦しめた問題を司法解剖するようで読み応えがある。つまりは「軍政」と「軍令」という独立した問題。所謂「統帥権の干犯」。2021/05/27
templecity
13
軍人出身の東条英機は政治家になってもその精神を回りや国民に押し付けた。几帳面で潔癖な性格であった故、その反映であり、融通もきかなかったのも確かであろう。一方で大日本帝国憲法の統帥権の独立に悩まされたのも確かであろう。陸海軍は内閣とも独立しており相互の連携も取れない。天皇のみが権限を持つが実行的には無理。開戦直前の中国撤兵の米国要求も陸軍の強い反対により実現できていない。陸軍出身の東條でさえコントロールが効かない仕組みであった。(続きあり) 2020/11/07
電羊齋
11
戦時指導者としての東條英機、特に首相、陸相、参謀総長の三職を兼任した1944年に焦点を当てている。「明治のシステム」すなわち内閣、陸海軍の諸機関が並列的関係であり、政治と軍事の統一が困難であるという限界点を克服するための兼任であったが、それは結局東條の仕事を増やしただけに終わり、サイパン陥落後東條内閣は崩壊を迎える。著者はそこに「明治のシステム」の限界を見出している。本書は、一ノ瀬俊也『東條英機―「独裁者」を演じた男』とはまた違った視点があり、併読してみると面白い。2020/10/04
-
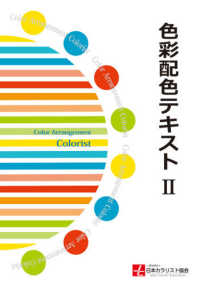
- 和書
- 色彩配色テキスト 〈2〉








