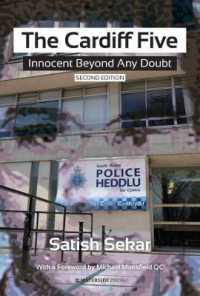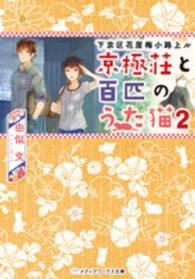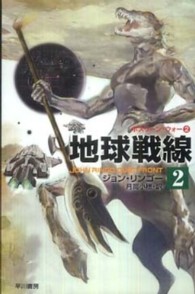内容説明
新元号の基となった、『万葉集』梅花の歌三十二首并せて序―。その作者・大伴旅人とは。有力氏族の嫡流に生まれた旅人は、藤原氏が隆盛を極めていくなか、時に政治抗争に巻き込まれ、平穏とは言いがたい一生を送った。いっぽう、酒を讃める歌、自然を愛でる歌、亡き妻や故郷を想う歌など、多種多様な歌を詠む。旅人の生涯をたどり、全作品を収録、すべて解釈つき。
目次
第1章 家系と出生(当時の婚姻形態;大伴安麻呂と巨勢郎女との婚姻形態;旅人にとってのフルサト「栗栖の小野」で、なんのための「手向」をするのか)
第2章 在京時代(生涯;秀歌鑑賞)
第3章 大宰府時代(生涯;秀歌鑑賞)
第4章 帰京後(生涯;秀歌鑑賞)
著者等紹介
中西進[ナカニシススム]
国文学者。1929年、東京都生まれ。東京大学文学部卒業、同大学院博士課程修了、文学博士。筑波大学教授、大阪女子大学学長、京都市立芸術大学学長等を歴任。現在、高志の国文学館館長、国際日本文化研究センター名誉教授、大阪女子大学名誉教授、京都市立芸術大学名誉教授。1994年に宮中歌会始召人。2005年に瑞宝重光章、2013年に文化勲章を受章。著書に『万葉集の比較文学的研究』(読売文学賞、日本学士院賞)、『万葉と海彼』(和辻哲郎文化賞)、『源氏物語と白楽天』(大佛次郎賞)、『中西進の万葉みらい塾』(菊池寛賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
64
【人もなき空しき家は草枕旅にまさりて辛苦(くるし)かりけり】「酒を讃める歌」や亡妻や故郷を想う歌など多様な歌を詠んだ旅人の生涯をたどり、全作品を収録し解釈した新書。<要するに彼は、人間、役に立つか立たないかなどと考えながら生きるのは止めて、それを超越して生きることを、モットーとしたらしい。一々そんなことに心を苦しめるより悠然と生きるほうがよい、というのだ。その結果に必ずすばらしい生涯が残されるという信念が、人間をどれほど賢くするだろう。人間が泥まみれになって生きる醜さが、どれほどか救われるだろう>うん。⇒2023/08/21
しゅてふぁん
51
出生から在京時代、大宰府時代、そして帰京後という人生の各ステージを歌と結びつけて旅人の生涯を解説した一冊。中西氏などによる秀歌鑑賞もあり、巻末には旅人が詠んだ歌が全歌掲載されていて嬉しい♪中国文学をすっかり自分のモノにして、それを和歌で表現するという旅人の教養の深さや風雅の心は本当に凄い。本人には不本意だろうけど、大宰帥になってなかったら憶良と出会うこともなく(もしかしたら歌を詠むこともなく)、作品がこんなに残ることもなかったと思うと大宰府左遷ありがとう!と声を大にして叫びたい(笑)2019/10/01
はちめ
7
中西進にあやかった軽いアンソロジーかと思いきや、1989年に出版された本の再刊ではあるが本格的な評伝だった。学者と歌人が複層的に旅人の歌と人生を評していて面白い。旅人の和歌作品は太宰府の卿として赴任して後の作品がほとんどなわけだが、その理由はそれ以前においては和歌を作る習慣がなかったというのが正解だと思う。赴任後すぐに最愛の妻を亡くしたことと山上憶良という歌友の勧めで歌を作るようになったのだと思う。梅花の宴で知られる筑紫歌壇も実質は憶良が作ったものだったのだろう。薄いけど読み応えがあります。☆☆☆☆★2019/09/13
れいまん
2
旅人特集だからこれ一冊に旅人のすべてが網羅されている有り難い本2022/05/18