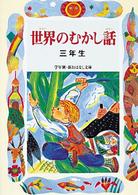出版社内容情報
常見 陽平[ツネミ ヨウヘイ]
内容説明
これが、残業大国・日本の正体だ!「残業」には、わが国の労働社会の問題が凝縮されている。「残業」は僧らしいほど合理的だ。そもそもが、日本の労働現場は残業しなければならないように設計されているのだ。本書では、この問題にいかに立ち向かうべきかを深く掘り下げて議論し、政府が進める「働き方改革」についても、その矛盾を鋭く指摘する。すべての働く日本人に、気付きを与える一冊。
目次
第1章 日本人は、どれくらい残業しているのか?
第2章 なぜ、残業は発生するのか?
第3章 私と残業
第4章 電通過労自死事件とは何だったのか?
第5章 「働き方改革」の虚実
第6章 働きすぎ社会の処方箋
著者等紹介
常見陽平[ツネミヨウヘイ]
働き方評論家、千葉商科大学国際教養学部専任講師。1974年生まれ、北海道札幌市出身。一橋大学商学部卒業、同大学院社会学研究科修士課程修了。リクルート、バンダイ、クオリティ・オブ・ライフ、フリーランス活動を経て2015年4月より現職。専攻は労働社会学。働き方をテーマに執筆、講演を行なう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
81
タイトルにひかれて読んだ。残業の実態はよく分析されていると思う。そして何が課題かについても。しかし最後には働き方改善ではなく「働き方改革」やトヨタ生産方式が社会を変えるなどの記述には違和感あり。そのトヨタ式生産方式の前工程、」すなわち部品メーカーや運送会社やたとえば通信会社だったりする。そう考えるとお客様は自分でもありお客様に提供する側でもあると思う。社会全体が輪になっているのかも。結局は日本全体の仕組みに問題があるのではないか。昔から続いてきた働き方を改革するにはまだまだ時間と個人の考え方が変わらねば2017/06/18
きいち
46
「働き方改革」への違和感。いい方向のはずなのに、何か引っかかる。その理由がわかる。仕事の任せ方や業務プロセスのことはスルーしてダラダラ残業やイケてない会議、ムダ資料などを槍玉にあげることで、問題点が働く個人の側にあるかのように扱われてるんだ。これこそ印象操作じゃないか。残業の合理性をもたらす日本の職場のマネジメント手法にこそメスを入れねば。◇生産性は付加価値/労働時間。となると、例えば介護や保育といった対価があまり支払われていない分野では、数字が低くなってしまう。こちらは制度の問題として改善が求められる。2017/06/16
けんとまん1007
44
働き方改革が叫ばれていて、事例としても、いろいろ巷に流れている。それを知るたびに思うことがある。表面的なことだけで、本来、あるべきところには、まだまだ至っていないということ。考え方として、枠を狭めることで、その中でどうするかを考えるようになる・・・ということもあるかもしれない。付加価値とは、存在意義とは、価値観とはのようなところにも結び付くと思うのだが。いろんなデータが示されているが、それ自体も、疑うことも必要。データのとり方次第で、結果は、かなり違ってくる。経済が良くなっている実感がないことが本質。2017/12/30
Miyoshi Hirotaka
33
ウルトラマンの地球上での勤務時間は三分間。仮に、時給制にしたら地球に平和をもたらすという崇高な使命に危険を顧みず立ち向う動機は刺激されない。現に、最終回では、ゼットンに倒された。残業問題もこれに似ている。限られた時間で最高のパフォーマンスを発揮するためには、実勤時間の他に、成長につながる自己研鑽、家族や地域社会に貢献するための時間が必要。勤務時間内の仕事の質は会社業務とは非関連と思われる時間の使い方により、品質が決まる。会社業務に迎合した教育訓練は即効性があるが、持続性に欠け、長期的な競争力にならない。2018/07/03
cape
26
自身の経験も踏まえて、問題の本質に迫ろうとする著者は、メディアの情報や大きな組織の声に翻弄されて、表層的な問題解決に走りがちな社会に一石を投じている。日本人の労働時間の推移や電通問題、働き方改革ブームに対する視点は、多くの人が認識を改めさせられるだろうと思う。著者の主張はもっともだと思うからこそ、もう少し踏み込んだ具体策や処方箋も提示してみてほしかった。いずれにせよ、本書は働き方改革、残業問題についての考察としては、そんなに悪くないのではないかと思う。参考にしたい。2017/07/05