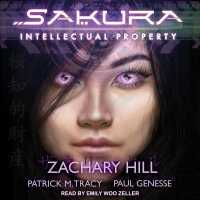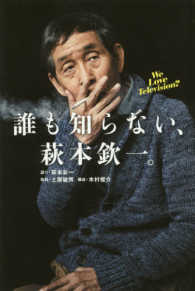出版社内容情報
大水の出る場所は、決まっている!
日本列島の水の手はどこで切れるのか?
【本書の目次から】
◎古記録が記す関東北部の沼沢群
◎カイト地名の実態は? 水街道とは?
◎決壊地点の対岸にあった「押切」という地名
◎龍ヶ崎市の「龍」は何を意味するか
◎千間堀がいつの間にか「せんげん台」に
◎オゴセ(越生)とは「驕る瀬」のことか
◎日本の地名は、ほとんどが災害に関連する
◎目黒川は「メグル(曲流)川」
◎継体天皇はなぜ樟葉宮で即位したか
◎六甲山地と灘が危ない
◎地名の「御影」は「水・欠け」のことか
◎なぜ「坂の町」長崎に、県庁が置かれたのか
◎「緑の丘」の中腹は危険きわまる
◎大字「八木」とは、どんな地名か?……
■地名研究半世紀の成果がここに!
災害大国・日本でもことさら多いのが水害。この四半世紀で1300件以上発生し、死者・行方不明者は1700名近くにのぼる。なぜ、これほどまでに多いのか? 自然の宿命もさることながら、水の出やすい旧城下町に人口が集中していることも大きく、人災である側面も否(いな)めないのだ。
繰(く)り返される水害を防ぐべく、古(いにしえ)より人は地名に思いをこめて警鐘を鳴らしてきた。かつては海であり、沼沢(しょうたく)や砂地、川があった場所、何度も土地が崩れた地点には、必ず鍵となる語が地名に残されている。例えば、崎、龍、瀬、狛、駒――の字が警告するものは何か? この日本で危ない場所は、すでに決まっている!
内容説明
災害大国・日本でもことさら多いのが水害。繰り返される水害を防ぐべく、古より人は地名に思いをこめて警鐘を鳴らしてきた。かつては海であり、沼沢や砂地、川があった場所、何度も土地が崩れた地点には、必ず鍵となる語が地名に残されている。例えば、崎、龍、瀬、狛、駒―の字が警告するものは何か?この日本で危ない場所は、すでに決まっている!地名研究半世紀の成果がここに!
目次
1 古代以来の沼地を都市化した愚―平成二七年、鬼怒川水害を検証する
2 地下街・地下室“水責め”の恐怖―平成一一年、博多駅・新宿区西落合、そして東京直下型地震
3 『岸辺のアルバム』の悪夢―昭和四九年九月、多摩川椿防決壊水害
4 古代都宮の周辺は“水浸し”の地だった―京阪神には畿内の大半の水が集中する
5 災害のデパート・名古屋の宿命―海と台地と扇状地、輪中の狭間で
6 “坂の町”長崎がなぜ危ないか?―昭和五七年、長崎大水害
7 「緑の丘」願望の破綻―平成二六年、広島安佐南区の土砂災害
8 江戸前期、熊沢蕃山の先見の明―昭和九年九月、岡山市大水害
9 シラス台地で繰り返される悲劇―平成五年、鹿児島市大水害
著者等紹介
楠原佑介[クスハラユウスケ]
1941年、岡山県生まれ。京都大学文学部史学科(地理学)卒業。出版社勤務を経て、地名についての著述活動に入る。「地名情報資料室・地名110番」を主宰し、正しい地名の復興に尽力(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
naginoha
鈴
くまくま
瓜月(武部伸一)
kira


![ふくふくこねこ [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42950/4295019534.jpg)