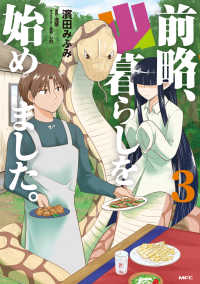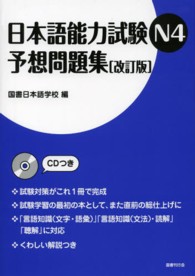内容説明
滞日五〇年、『フィナンシャル・タイムズ』『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』の各東京支局長を歴任し、三島由紀夫とも親交を結んだ英国人大物記者が、戦後、戦勝国の都合で作り上げられた「日本悪玉論」を断罪。南京事件、靖国参拝、従軍慰安婦などの問題について論じ、さらに三島が死を賭して訴えようとしたものが何であったかを問いかける。来日当時は戦勝国史観を疑うことなく信奉していた著者は、いかにして考え方を大転換させるに至ったのか。
目次
第1章 故郷イギリスで見たアメリカ軍の戦車
第2章 日本だけが戦争犯罪国家なのか?
第3章 三島由紀夫が死を賭して問うたもの
第4章 橋下市長の記者会見と慰安婦問題
第5章 蒋介石、毛沢東も否定した「南京大虐殺」
第6章 『英霊の聲』とは何だったか
第7章 日本はアジアの希望の光
第8章 私が会ったアジアのリーダーたち
第9章 私の心に残る人々
終章 日本人は日本を見直そう
著者等紹介
ストークス,ヘンリー・S.[ストークス,ヘンリーS.] [Stokes,Henry Scott]
1938年英国生まれ。61年オックスフォード大学修士課程修了後、62年フィナンシャル・タイムズ社入社。64年東京支局初代支局長、67年ザ・タイムズ東京支局長、78年ニューヨーク・タイムズ東京支局長を歴任。三島由紀夫と最も親しかった外国人記者としても知られる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyoshi Hirotaka
73
G8で有色人種国家はわが国のみ。黒人大統領誕生は公民権運動から約60年かかった。南アのアパルトヘイトは1994年まで存在した。況や、第二次世界大戦までは白人が有色人種を支配するのは文明化という「正義」。500年続いた常識をひっくり返したのは、日露戦争と太平洋戦争。白人国家による植民地支配の終焉は、20世紀で最も大きなパラダイムシフト。連合国、つまり白人戦勝史観は行き詰る。これに便乗し、わが国を邪悪とする中韓のプロパガンダも破綻する。戦後レジームからの脱却とは、大きな歴史の流れにわが国を位置付けることだ。2015/06/29
ベルるるる
47
著者は三島由紀夫と親しかった。自決直前、三島から手紙、論文、小説が送られてもきた。三島が命に替えても守らねばならなかったものを、三島から託された遺言とでもいうものを、著者は書き残さねばならなかったのだと思う。自衛隊員に訴え、「馬鹿野郎、チンピラ」と罵られ、絶望し、そして死んでいく三島。命を絶った事で、あの時の命を絶たねばならなかったほどの絶望、そして三島の願いは今も語られている。2017/07/01
ヘタ
41
本書での対米戦争に関する著者の主張は、今ではあまり論争の対象にならなくなっているように思う。リベラルな方々も、受け入れつつあると思う。そうであっても、これが圧倒的多数とは言いがたい。この主張を海外に向けてだけでなく、いや、国内でこそ声高に叫ばなければならないところにわが国の不幸があると感じた。戦後、西と東に分断されずに済んだ。本当によかったと思う。しかし、約70年経ってもあの戦争を総括できないことを思うと、分断されなかったことにも負の部分があると感じてしまう。(そもそもあの戦争をなんと呼ぶのか。)2014/07/21
kawa
37
著者は永年「ファイナンシャル・タイムズ」「ザ・タイムズ」「ニューヨーク・タイムズ」の日本支局長として活躍した英国人。自らが少数派のクエーカー教徒と言う出自もあって、欧米多数派の白人から差別されたユダヤ人や日本人に親しみを感じると言う。付き合いのあった三島由紀夫や日本・アジアの大物政治家評は事の真偽をともかく読んでいて興味がつきない。表題の「連合国戦勝史観」は、日頃思っているところからは違和感70%位は残る内容。なるほどと言うところが無い訳ではないので、それらを尊重した上で検討できる機会があれば良いかな。2025/08/05
№9
32
Amazonのレビューを見ると、翻訳の一部に問題があるらしい。しかし、それをもって本書にある著者の主張がすべて信用できないとか胡散臭いとか言えるだろうか。歴史を学ぶにつれこの国際社会には「普遍的な国際正義」などあり得ないのだと暗澹たる気分になる。自国の国益のみを考えるプロパガンダと工作合戦こそ国際社会の素顔だ。だから日本もまた自国の立場を正々堂々と主張すればいい。日本の歴史と文化とその魂に多くの外国人の方々が触れたとき、真実は何かと探し始め、日本人よりも明快にそれに答えてくれる。そんな一冊であると感じた。2014/12/01