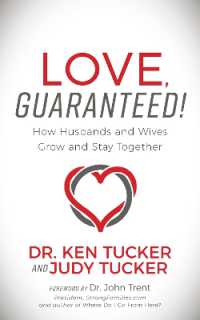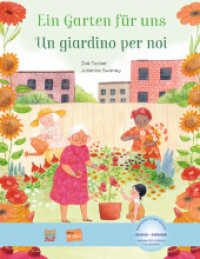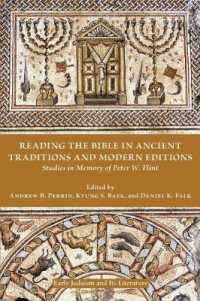出版社内容情報
赤本、青本、黄表紙、合巻と形を変えていった草双紙は、いわば江戸の
漫画本。そこでは化物たちが縦横無尽に動き回ります。草双紙の中で、化物たちは人間の生活様式を真似ながらも、化物の価値観はそのままなので、不思議な異次元世界が展開します。
たとえば・・高望みのお見合いをしたいので、できるだけ汚くて醜い嫁が来てほしい化物。引っ越し先の部屋がきれいすぎるので、わざと部屋を壊して汚くし、自分にとって住みやすくする化物。田舎なら出てきたが仕事がなく、せっぱつまって生まれつき巨大な金玉を貸し布団にすることにし、そこに何人もの人を寝かせて金を取る狸の話も。バカバカしくもシュールで超現実的な世界が、草双紙です。
著者は絵に添えられたくずし字の説明を読み解き、江戸の町民を沸かせた化物たちの世界をわかりやすく解説します。あわせて代表的な化物の性格・
特徴を紹介しながら、彼らがどうして江戸っ子に熱狂的に愛されたのかを分析していきます。アメリカ人研究家だから解明できた、可愛らしくて、
奇想天外な化物の世界がここに!
【著者紹介】
954年 アメリカ・ニューヨーク州生まれ。アメリカ人の日本文学研究家。武蔵大学教授。専攻は近世日本文学。東京大学大学院総合文化研究科博士課程中退。主な著書に『大江戸化物図鑑』(小学館)『江戸滑稽化物尽くし』『ももんがあ対見越入道―江戸の化物たち』(ともに講談社)、編著に『江戸化物細見』(小学館)なのがある。
内容説明
江戸時代後期の娯楽本・黄表紙は、当時の世相や流行を巧みにパロディ化した絵入り小説本で、一世を風靡した。この本で大活躍するのが、化物たちだ。彼らは人間社会とは違った独自の価値観で、人間の生活様式を真似る。その姿は、庶民の生活を映し出す合わせ鏡の役割をはたし、ユーモアあふれる奮闘ぶりは、今読んでも軽快な笑いを誘う。本書は、「見越入道」や「豆腐小僧」などの化物たちが繰り広げる奇想天外なストーリーを現代の生活事情に見立てた、新しい「化物案内」である。
目次
序章 江戸時代、化物が活躍した舞台
本章 現代の用語で読み解く化物の世界(住宅事情;職業;会議・研修;仕事上での悩み;恋愛・セックス;美容・ファッション;夫婦関係・結婚;親子関係;健康;趣味)
著者等紹介
カバット,アダム[カバット,アダム][Kabat,Adam]
1954年、アメリカ・ニューヨーク生まれ。1981年に来日し、東京大学大学院比較文化比較文化専攻課程を経て、武蔵大学教授。専攻は日本近世文学。江戸時代の妖怪、化物について独自の視点で研究を重ねる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たみ
かりこ
honey
紅独歩
スプリント