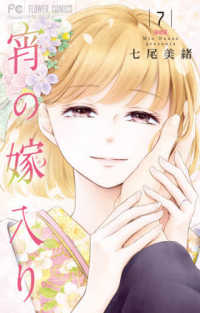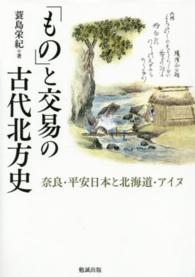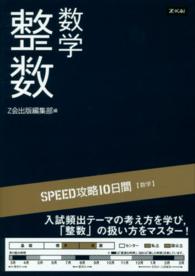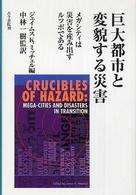出版社内容情報
歴史から見た日本人
「よく生きる」とは何か
死に臨んで故郷をめざした道元や日蓮。
日本人離れしていた信長の死生観。
彼らは昏迷の時代をどう生きようとしていたのか
末法思想の圧倒的な影響のもとに痛ましく死に急いだ人々。平維盛は、なぜ生きながらの浄土を求めたのか。また早良天皇、菅原道真、崇徳上皇たちは、死後、魔妖となって復活したと恐れられた。そうかというと、死に臨んで故郷に帰りたがった親鸞、道元、日蓮たち高僧の人間らしい姿。恥をさらすより、潔く死して名を残すことを重んじた日本人たち ……。
歴史から垣間見える、さまざまな死のかたちを通して、現代人にとって真に生き、真に死ぬとはどういうことか、その本質にせまる。
織田信長は、本能寺の変のとき、一万数千の明智軍に向かって最後の抵抗をした。彼の美学はそんな未練を許さなかったはずだ。しかし、そこには信長の日本人離れした死生観が隠されていたのである。
彼岸憧憬 ── 平維盛(これもり)たちの熊野。何が、彼らを死に急がせたのか
魔界転生 ── 早良(さわら)天皇や道真。新たな生を得た、と恐れられた人々
臨死望郷 ── 故郷恋慕。大和武尊の白鳥伝説、そして道元、日蓮も
天帝昇天 ── あの織田信長は、死生観までも日本人離れしていた
不借身命 ── 美、主義、信仰。それらに殉じた日本人の美意識とは
殉死三腹 ── 埴輪(はにわ)から乃木大将まで、日本的なるものの秘密を探る
史上空前の長寿時代のいま、死はあらためて考え直される必要があるのではなかろうか。ある人の死に方は、いわばその人の生き方の総体である。死の場面に凝縮されて浮かびあがってくるものが、その人の生き方を象徴するという意味で、どちらかというとふやけかかっている現代人と死の関連について、歴史から学びとれる事がらを書いた。 歴史的事実として、ふだん見過ごしてしまうものでも、死という局面から捉えかえすと、そこには、意外な真相が見えてくる。この人間くささが本当の歴史なのかもしれない。(著者のことば)