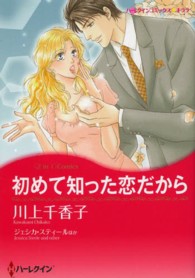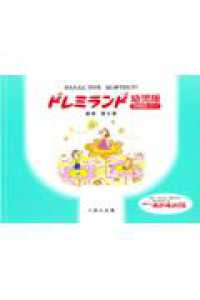内容説明
建築家と小説家は何を構築し何を破壊したのか。「建築からの文学史」であると同時に「文学からの建築史」である。しかしそれだけではない。明治・大正・昭和という一続きの時代への日本人の心の空間を旅する紀行である。
目次
辰野金吾と夏目漱石の時代(開化の時勢;煉瓦と下宿)
後藤慶二と谷崎潤一郎の時代(モダンと田園;個室と密室)
坂倉準三と川端康成の時代(起ち上がる美と滅びゆく美;戦火の下で)
丹下健三と安部公房の時代(日章の名残;成長という破壊)
著者等紹介
若山滋[ワカヤマシゲル]
1947年台湾生まれ、東京都出身。1969年東京工業大学建築学科卒業。1974年(株)久米建築事務所入社。1976年東京工業大学大学院博士課程修了、工学博士。1983年名古屋工業大学建築学科助教授。1989年同教授。現在、中京大学、放送大学、椙山女学院大学、各客員教授、武蔵野美術大学非常勤講師、名古屋工業大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Crack Luc
3
東京駅やニコライ堂といった建造物を改めて訪れたくなるし、夏目漱石や安部公房の作品を読み返したくなったり。日本の建築や文学の魅力を再確認させてくれる、素敵な本でした。2025/04/06
史縁
1
明治~昭和まで、各時代の建築家・建築様式の変遷、小説に登場する建築と話のストーリーでの位置付けについて自説を展開。夏目漱石と辰野金吾、谷崎潤一郎と村野藤吾、川端康成と坂倉順三。坂口安吾とタウト。同じ関西でも、谷崎潤一郎の洋風=上流階層と織田作之助のミナミ=庶民の住居 の差。建築というより文学寄り。取り上げる時代が広いので、1つの作家を掘り下げればもっと面白いのではないか。2024/06/09
yuma
1
建築家と小説家は本質的に同じであり、その職に男性が多いのも分かる気がした。現代文学指南書としても非常に面白い。2016/05/06
あらなみ
0
図書館本。表題に似つかわしくなく、内容は近代から現代における小説家視線で展開される。筆者は建築の門の出であるはずなのに。 申し訳程度に出てくる建築家とその作品、主軸は筆者の選り好みした小説家が作品にえがいた当時の建築とその役割。 近代小説入門には良いかもしれないが、うっかり、小説家の住んだ家や地域の建築様式紹介と思って借りた自分にはきつい内容だった。 ちょっと何が言いたいのか、わかんねぇっす。2017/12/10
こさと
0
地元図書館の本。2014/06/26