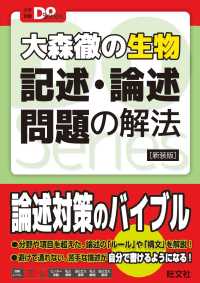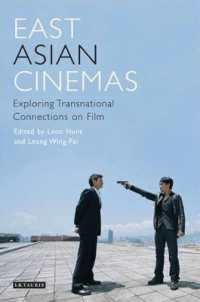目次
はじめに 着物は日本文化の宝庫
第1章 全てのきものは「素材」が大切
第2章 「身体」を知り自由に楽しむ
第3章 きものの正しい「名称」を覚える
第4章 「作法」で美しい振る舞いを
第5章 きものは「経済」を教えてくれる
おわりに ご自分で着物の扉を開けてみて
著者等紹介
中谷比佐子[ナカタニヒサコ]
きもの文化研究家、きものエッセイスト、きものジャーナリストとして活躍。大分県出身。共立女子大学文芸部卒業。女性誌の編集記者を経て「秋櫻舎」を設立。きもの季刊誌『きもの秋櫻』を発行。きものを切り口に日本の文化、日本人の考え方の基本、美意識を学び伝承している。農林水産省蚕糸業振興審議会委員として、国産シルクブランドの開発に携わる。平成25年「蚕糸功績賞」を財団法人大日本蚕糸会、正仁親王より拝受(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふう
18
目から鱗の数々。和裁で疑問に思ったあれこれが解明できた。右がかった精神論はともかくとして、理論的に納得できることも多く、面白かった。みょうが巻き? 調べても食べる分野のことしか出てこない。下着の話など、図解が欲しいところも多い。既にわかっている人にしか分からない言葉は解釈不能。80代の方々へのインタビューでびっくり。現代は生理用品に頼って自分の感覚に鈍感になってしまっている、と。今更だけれど、自分の体を意識する大切さは今も必要。2026/02/03
KUMYAM@ミステリーとSF推し
3
科学的根拠や歴史的事実に基づいた解説は分かりやすくとても勉強になった。が、どうしてもそこにスピリチュアルな解釈を捩じ込んでくるのに辟易した。着物が日本の誇る文化であることに異論はないが持ち上げすぎるのは他国に失礼かと。2025/11/10
Natsu K
3
内容としては、着物に関する雑学が寄せ集めてあって面白かった。ただ、着物と日本文化、「古き良い日本」への盲目的な信奉が言葉遣い含め随所に顕れていて居心地が悪い。上の世代の人の話を聞く時によくある違和感。2023/02/13
しゃむ・しゃむ
0
着物に関する様々な知識。2023/03/27
かすもり
0
着物に関連するあれこれを初めて学ぶのに取っ付きやすそうだったので図書館で借りてきた。野生の蚕から改良した養蚕は食べさせる葉の種類などにより、更に綺麗な絹糸になること、各素材の特徴と使用例、着物の名称と役割、細かな作法など全体的に興味深く読めた。圧倒的な自我が多少目に付くけど、「(昔の人は)一つの着物を工夫して春夏秋冬来て過ごす(p57,1-2行)」事、「胸当ての存在とその有用性」など、着物の知識がほぼ無い人間にもわかりやすく伝わる書き方、注釈でとても勉強になる。言葉の説明が豊富で良心的。2021/04/29
-

- 洋書
- Nanobytes
-
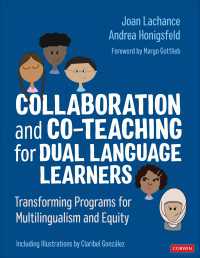
- 洋書電子書籍
- Collaboration and C…