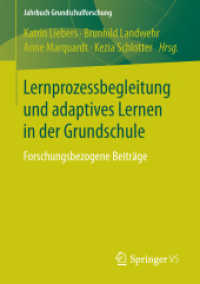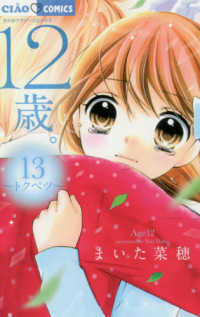内容説明
私たちは、言葉を介して、精密な情報のやり取りができているだろうか。理屈無き「共感」に流されてはいないだろうか。現代における雑駁な日本語表現を添削し、伝えたいことを明確にした文章作成法・言語表現法を学ぶ。その具体例として、寺山修司や塚本邦雄といった前衛歌人たちも影響を与えた斎藤茂吉を中心に、短歌の表現を読み解いていく。震災後の言語の変化も視野にいれながら、より良いコミュニケーションのための日本語使用法を知る。
目次
第1部 いまの日本語(「“ことがら”情報」の言語化:ゆるむ枠組み;もっと簡単に!情報と言語量;バランスのよい言語化)
第2部 感情・感覚の伝え方(斎藤茂吉の短歌をよむ;茂吉と二人の歌人;災後の日本語を考える)
著者等紹介
今野真二[コンノシンジ]
1958年神奈川県生まれ。1986年早稲田大学大学院博士課程後期退学。高知大学助教授を経て、清泉女子大学教授。専攻は日本語学。主な著書に『仮名表記論攷』(清文堂出版、第30回金田一京助博士記念賞受賞)他、多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
多分マグマグ
2
ことばを磨く。再読する2023/12/06
Go Extreme
1
人間と言葉の関係 はなしことばと書きことば ことがらと感情 いまの日本語:事と心 抽象と具体 ことが情報の言語化ーゆるむ枠組み:筋を通す 対義・対句 類語 比喩表現 情報と言語量:抽象と具体 皆さんとわたしたち 抽象と具体のバランス 修飾部分に着目 詩歌のパラフレーズ バランスのよい言語化:ことがらと感情 比喩 共感 感情・感覚の伝え方:言語を共有すること スペイン風邪 自然と自己がひとつになる視点 2021/01/09
ベルモット
0
「書き言葉」と「話し言葉」、「ことがら情報」と「感覚情報」、「具体」と「抽象」……主張は何となく伝わるし、より丁寧に言葉を扱うべきだと感じることはできた。ただ、私なんかが言うことではないが、筆者の文章は本当に伝えたい情報を伝えられているだろうか。読者に問いかけている割には、筆者も自身の思考を具体的に言語化できていない。引用は飽くまで補足としてしか作用しない。その為に説得力が不足している気がするのだ。更に、敢えて、というのもあるだろうが、斜に構え過ぎではないか、特定の個人を美化し過ぎてはいないか、と思う。2021/04/09