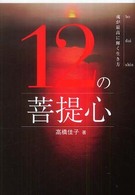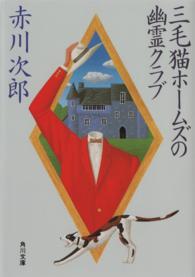内容説明
脳科学・身体運動学からひもとく音楽する脳と身体の神秘。
目次
第1章 超絶技巧を可能にする脳
第2章 音を動きに変換するしくみ
第3章 音楽家の耳
第4章 楽譜を読み、記憶する脳
第5章 ピアニストの故障
第6章 ピアニストの省エネ術
第7章 超絶技巧を支える運動技能
第8章 感動を生み出す演奏
著者等紹介
古屋晋一[フルヤシンイチ]
音楽演奏科学者。ハノーファー音楽演劇大学音楽生理学・音楽家医学研究所研究員。大阪大学基礎工学部卒業後、医学系研究科にて博士(医学)を取得。日本学術振興会特別研究員、海外特別研究員、フンボルト財団招聘研究員を歴任。「ランランと音楽を科学しよう」(SONY)において講師を務めるなど、国内外で講演を行う。主なピアノ演奏歴として、KOBE国際学生音楽コンクール入賞、Ernest Bloch音楽祭出演、兵庫県立美術館にてリサイタルなど(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
pino
130
ピアニストの脳の地図は長年の訓練により書き換えられ、ピアノ演奏に特化しているという。脳のケーブルを包む鞘や脳部位の体積はアマチュア演奏家よりも大きく、また特殊な脳回路や優れた聴覚野の存在は精度の高い洗練した演奏に繋がっている。体中のセンサーをフル活用して、人々を魅了するピアニストの能力は、遺伝?いえ。幼少期からの練習の賜物だそう。一方で手指が思うように動かせなくなる病についても頁を割いている。ピアニストの故障はアスリート並だと知った。著者の「科学で芸術をサポートしたい」という切なる願いも溢れ出ている良書。2017/05/15
パフちゃん@かのん変更
85
ピアニストは感性豊かな芸術家であるとともに、高度な身体能力を持ったアスリートであり、優れた記憶力、ハイスピードで膨大な情報を緻密に処理できる、高度な知性の持ち主。小さい頃からのたゆまぬ努力が必要と言われますが、11歳までの練習はすればするほど鞘を発達させることができるらしい。どれくらい練習すればいいかというと、一日当たり平均3時間45分の練習が演奏技術を維持するために必要。しかしイメージトレーニングをしてそのあと普通に練習すればイメージトレーニングの時間も練習したことになる。あと、大切なのは脱力と姿勢。2015/10/26
HoneyBear
55
やっぱり楽器を幼少時に本格的にやると脳の機能に大きな差を生むようだ。アインシュタインもプロ並みのヴァイオリン弾きだった。確かに楽譜や音などの多くの情報を瞬時にプロセスして複雑な司令を指先に伝えるのだから脳の成長に寄与するだろう。その差が、脳の「省エネ」(無駄な経路を使わず効率的に情報・司令を伝達)の巧拙からくるというのが面白い。私は何も楽器を学ばなかったのが本当に残念だ。脳に効くくらいに楽器をやるとなると手や指を痛める危険があるスポーツなどはできなかったのだから… と自分で慰めている。2014/01/10
あやの
44
「ピアニストは省エネの達人」これに尽きるようだ。高速で弾いているときも、筋肉の動きはもちろん省エネだが、脳細胞も活発に働いているわけではないのだとか。筆者はピアニストの脳や筋肉について多くの実験を行っているとのこと。本書も様々な実験結果を紹介してくれている。この内容をぜひ映像で見たいものだ。文字で読むだけとちがって、興味深いものになるだろうなと思う。大人になってからでも毎日練習することは無駄にならないということで、それは励みになった。ピアニストがその力を維持するには1日に3時間45分の練習が必要!2023/12/17
ひめか*
44
ピアノ弾きにとっては読むべき一冊。ピアニストの脳、実に興味深い。やはり毎日ちゃんと練習する、音を聴くことは大事だな。一番衝撃だったのはイメージトレーニングの効果。旅行に行った時などピアノ弾かなくても、ピアノ弾いてる指の動きを思い浮かべるだけで、帰ってきてから練習すると、同じ期間弾いて練習したのと同じ程度まで脳の働きは向上する!これは使える。脱力や指の独立は、無意味な筋力を使わずに疲れないためにも大切。肩から腕、肘の使い方ももっと上手にできるようになりたい。音楽を多く聴くことも重要だと思った。参考になる!2015/10/03