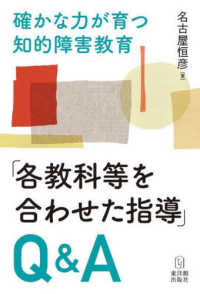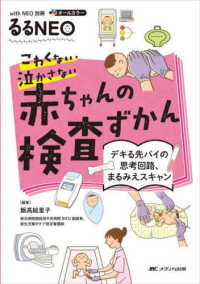出版社内容情報
死とは、生とは何かを、アニミズムをヒントに思索。生命とは別の、誰かの心に生き続ける〈いのち〉について思索する哲学エッセイ。
内容説明
人は、死んでも消え去らない。そのことを、私たちは経験的に知っているのではないだろうか?韓国学者が、“いのち”のありかを探る哲学エッセイ。
目次
第1章 死んでゆく人に(「あっ」と気づくことが“いのち”;「わたし」は知覚像の束である;いまこのように見えていることには理由がある ほか)
第2章 わたしはどこにいる(このように感じ、考えていることが、わたし;“ことかげ”は無数の他者によって生まれる;“ことかげ”の束が成り立つ場)
第3章 “いのち”のかがやき(生命を嫌悪すること;自分にとって“いのち”となるもの;見つめあうこと)
著者等紹介
小倉紀蔵[オグラキゾウ]
1959年東京生まれ。京都大学総合人間学部、大学院人間・環境学研究科教授。専門は、韓国思想文化、東アジア哲学。東京大学文学部ドイツ文学科卒業。韓国ソウル大学校哲学科大学院東洋哲学専攻修士課程、同大学校哲学科博士課程単位取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
amamori
1
小倉先生が なんらかの実存的な危機の中でつかんだ自家製宗教哲学。星の王子様、大森荘蔵、道元などの素人っぽい張り合わせには親しみがわきます。誰もがこういう自家製哲学をもってるのでしょうから。いい対話相手になります。”<わたし>は生きていない”というテーゼとかも面白い。2013/09/08
taq
0
自分が生まれて生きて死ぬ、と当たり前に思っていることが、つぎつぎ覆されていって、最終的には<いのち>は<死なない>という驚くべき結論に連れていかれる。最終的な結論についてはまだ実感としてわかる段階には至っていないが、<ことかげ><たましひ><いのち>といった独特の概念をつかって自我が実体として成立していないことや、<いのち>は一般的に生きていると考えられている存在とは違うと見るあたりはとても新鮮で、ここからいろんなことを考えていけそうだ。尹東柱の詩の解釈は目からうろこのすばらしさ。2025/04/05