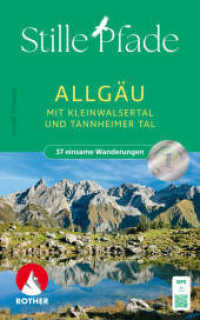内容説明
普遍論争、現代哲学を先取りする知識論、経済の基礎となる利子の正当化、「概念」という概念そのものの発明など、知られざる中世哲学の偉大な成果を、神の存在証明と天使の堕落問題を軸に、哲学史の常識をくつがえす新たな知見をちりばめて一挙に紹介。現代思想にも巨大なインパクトを与えずにはおかない革新的論考。
目次
第1部 中世とは何か(ヨーロッパ中世世界;天使と秩序世界;中世一〇〇〇年 ほか)
第2部 中世哲学の誕生と発展(キリスト教神学の成立―カンタベリーのアンセルムス1;神の存在―カンタベリーのアンセルムス2;天使の堕落―カンタベリーのアンセルムス3 ほか)
第3部 中世哲学の成熟と終焉(変化のきざし―ヨハニス・オリヴィ;ヨーロッパ中世終端間近の輝き―ドゥンス・スコトゥス1;存在の類比から概念へ―ドゥンス・スコトゥス2 ほか)
著者等紹介
八木雄二[ヤギユウジ]
1952年、東京生まれ。慶應義塾大学大学院哲学専攻博士課程修了。文学博士。専門はドゥンス・スコトゥスの哲学。現在、立教大学ほか非常勤講師、東京港グリーンボランティア代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
21
中世哲学通史として稀に見る水準の一冊。馴染みの薄いこの分野を背景となる時代から描き、完全に一つの哲学史として成立させているのは素晴らしい手腕。キリスト教化された新プラトン主義濃厚な中世哲学にとって、概念の世界は、まどマギの女神まどかのごとく実在であって知性はそれを認識するために必要不可欠なものだった。そうした普遍実在論とは異なる要素を持ち込んで近代哲学や科学を準備したのが、オリヴィ、スコトゥス、オッカムである、と。このボリュームでも正直さわりだけの感があるが、新鮮な知的興奮を大満喫2013/03/28
マウリツィウス
16
【西欧中世史古典の意義と検証】旧約権威から解放されていく新約像は必然的にギリシャ文明と同調していく。しかしその状況を打開すべく提示された哲学こそがスコラであるべきが天使像の偶像化につながる論点がここに示される。しかし、スコラとキリスト教融和論失敗要因は古代ギリシャの空間性尊重に由来する福音書構成の剥奪化と逸脱、成立課題はギリシャ詩人の構築したテクスト性を合一化したのではなくキリスト教派生異端を薙ぎ払う根源力権利を誇る。打倒すべき文書を吸収することで絶対権威を保持した《天使》はギリシャ知識と信仰知を振った。2013/06/15
さえきかずひこ
12
著者はまず7〜17世紀をおよそ西洋における中世と定義し、その概ね1000年間に営まれたキリスト教的な哲学について論じていく。本書を読み進めることで、中世哲学における重要な要素が、実在論と唯心論であること、またイスラム経由で獲得されたアリストテレス哲学にあること、そして新プラトン主義の流出説も大きな役割を果たしたことが自然と掴めてくる。哲学を介し学問化してゆくキリスト教=神学の形成についての指摘もこの時代の理解を深める点で見逃せない。入門としては大部だがつねに神を見やって思索した中世人に触れられる浩瀚な書。2019/07/19
mob
7
・馴染みにくい中世哲学だがタイトルで興味を引く天使論で理解の確認も進む優れた構成。・天使の身体性と堕落を論じれば、アンセルムスの段階で危うさを感じられる。アリストテレスも天使も守るなら戦線が多く綻びも目立つ。・筆者はスコトゥスを研究していて、そこにオッカムでの終焉への道筋を見ている。オリヴィも重要で、トマスが脇役気味。・科学が中世哲学を陥落させたのではなく、哲学の担い手が自ら城門を開いて崩壊の道を選んだ。これは進歩ではなく盛者必衰。現代の独善的価値観が自壊できるほど賢さを持つのはいつの日か。2021/04/18
roughfractus02
5
肉体は常に外に晒されている。上を向くという行為は、イコンを見て宇宙と繋がろうとする行為である。この時、肉体は中世のあの晒される恐怖を感覚している、なぜなら、見上げることは、全てを見下ろされる世界の存在を感覚することと同じだからだ、と著者はいう。十字架で悪魔を追い払う中世の人たちは、儀式を行ったのではなく悪魔に対してなす術のない恐怖を抱いたのだという。中世はこの肉体があるゆえに論理を発展させ、些末さにも陥った。が、ドゥンス・スコトゥスの言葉に秘めた生々しい欲求が、オッカムの剃刀に削がれた時、近代が始まる。2017/02/19