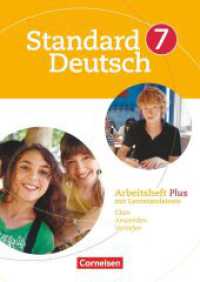出版社内容情報
生活のなかの民間伝承を入口に、自然やこの世ならぬものへの畏怖と歩んできた日本人の豊かな精神性を味わう。
失われたかに思われている民間信仰は、現代生活にも密かに息づいている。日頃の何気ない生活の断片のなかに、古からの智恵が受け継がれているのだ。節分や、土用のウナギ、歳神様、さらには妖怪伝承……。年中行事の考察を入口に、自然やこの世ならぬものへの畏怖とともに歩んできた、人間の豊かな精神性をたどる。
【著者紹介】
1963年生まれ。1992年筑波大学大学院博士課程単位取得退学、弘前大学、愛知県立大学を経て、現在、国立歴史民俗博物館教授。著書・編著書に、『伝承歳時記』『民俗学的想像力』『陰陽道の歴史民俗学的研究』、共著書に『シリーズ日本人と宗教〈第5巻〉 書物・メディアと社会』など。
内容説明
神仏・鬼・妖怪・精霊。人間はこの世ならぬ者たちと、どのように関わってきたのか。暮らしを通して受け継がれてきた精神性の源をたどる。
目次
春の章(節分の主役;豆にこめる力 ほか)
夏の章(端午の節供とその由来;休日の民俗的起源 ほか)
秋の章(七夕と盆と星と;盆棚の牛馬 ほか)
冬・新年の章(亥の子と十日夜;十夜念仏の民俗性 ほか)
著者等紹介
小池淳一[コイケジュンイチ]
1963年生まれ。1992年筑波大学大学院博士課程単位取得退学。弘前大学、愛知県立大学を経て、国立歴史民俗博物館教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
むつこ
23
日本各地で行われる季節の催事を紹介。神仏、妖怪、動物や自然と関わった先人たち。最近まで気にもしないで昔話を聞いていたこと、行事に参加していたことがもったいないと思った。廃れることなく続いてほしい地元の行事の必然性に気がつく一冊になってほしい。2016/02/02
海辻
2
多種多様の研究者の文献をまた引きしつつ、各季節の中で人々の隣にあった神や仏の姿を紹介する。民俗学、仏教民俗学を区別せずに、日本人に溶け込んでいる信仰を学ぶには良いかも。(図)2016/01/23
狐狸窟彦兵衛
2
日本の「神様」って、ものすごい超越した「何か」ではなく、すぐ隣にいる「モノ」なのですね。それが「福」をもたらすときもあるし、「厄」をもたらすこともある。「畏(おそ)れ」と「畏(かしこ)み」、「祝」と「呪」……。季節の移ろいの中で、その日の無事に感謝し、明日の幸いを祈ってきた人々の営みを、民俗学の文献を丁寧に紹介しつつ分かりやすく解説してあります。図書館で見つけたけれど、ずっと参考書にしたくて買い求めてしまいました。2016/01/19
まめ
1
[図書館]『歳時民俗は歴史学とは異なる時間や過去との接点であると同時に、そうした記憶や経験の重なりを文芸として表現しようとする際の拠りどころになるものである。』(P.207) ざっくり一年をめぐる。2015/11/12