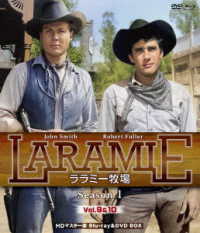出版社内容情報
韻文経典からゴータマ・ブッダと直弟子たちの教えに迫る
従来の研究では曖昧だった初期韻文経典と散文経典を明確に区別し、初期韻文経典の説示を通して、ゴータマ・ブッダや直弟子たちの最も古い仏教を考察し、韻文経典の段階で教理化が進んでいることを明らかにした画期的書。
「本書の目的はこの初期韻文経典の説示を通して原始仏教でも最も古い仏教を考察することにあるが、実はそこにも仏教興起時代の最古層から新層へと次第に展開し、後の優れた仏教修行者たちによってさまざまに解釈され教理化が進められていく展開がみられ、初期韻文経典も決して画一的に理解されるべき経典ではないことがわかる。つまり、初期韻文経典にはゴータマ・ブッダや直弟子たちの教えが説かれていると簡単に済ませられない数多くの問題点が存在しているのである。それを明らかにするためには、何よりもまず最古層の韻文経典において歴史的存在者としてのゴータマ・ブッダや直弟子たちの宗教体験に基づいて説かれた教えを精査し、それ以後の過程でその教えがどのように解釈されていったのか、その展開を比較研究することによって相違点を明確化する必要がある。」(本書より)
【目次】
略号表
凡例
はじめに
(一)問題の所在と研究方法
(二)本書の概略
第一章 四聖諦と三学
第一節 最古層経典にみるゴータマ・ブッダの教え
第一項 この世における人間存在
第二項 苦しみを脱する修行過程
第三項 苦しみから解き放たれた人とその境地
(一)苦しみから解き放たれ、悟りを体得した人
(二)悟りの境地
まとめ
第二節 四聖諦の成立
第一項 最古層経典にみる四聖諦に関する教え
第二項 古層経典とそれ以降における四聖諦説
(一)「四聖諦」と「四諦八聖道」
(二)「集諦」の規定
第三項 初転法輪の伝承に関わる初期韻文経典の説示
まとめ
第三節 三学の成立
第一項 初期韻文経典にみる修行
(一)最古層経典に説かれる修行
(二)古層経典に説かれる修行
(三)新層経典に説かれる修行
第二項 智慧(pa???)とは
(一)「智慧」の用法
(二)「智慧」の意義 ─「〔自己の存在を〕正しく自覚すること(sati)」と対比して
第三項 「三学」の成立
まとめ
第二章 「苦しみ」と「苦しみの起こるもと」
第一節 最古層経典にみる「苦しみ」と「苦しみの起こるもと」とは
第一項 「苦しみ」の原語 dukkha の用例
第二項 「苦しみ」と「苦しみの起こるもと」の用例
(一)「苦しみ」の用例
(二)「苦しみの起こるもと」の用例
(三)「苦しみ」と「苦しみの起こるもと」に関する最古層経典の立場
第三項 「苦しみ」と「苦しみの起こるもと」に対する無自覚と自覚
第四項 苦しみのない理想的境地
まとめ
第二節 「苦しみの起こるもと」とは
第一項 最古層経典にみる「苦しみの起こるもと」
(一)「苦しみの起こるもと」の用例
(二)「執着」と「渇愛」の関係性
(三)「渇愛」の意義
第二項 古層経典にみる「苦しみの起こるもと」
(一)「苦しみの起こるもと」の用例
(二)「執着」と「渇愛」の関係性
(三)「渇愛」と「無明」の意義――生存の根源として、縁起説の基軸として
(四) 「煩悩(kilesa)」 と 「随眠(anusaya)」
(五)「五蓋」の成立――煩悩の分類の始まり
まとめ
第三章 「自己の存在に対する正しい自覚」の宗教的意義
第一節 最古層経典における sata 、sati の用法
第一項 最古層経典にみる sata 、sati の語義
(一)sata 、sati に対する先学の訳語
(二
内容説明
韻文経典からゴータマ・ブッダと直弟子たちの教えに迫る。従来では一括りにされてきた韻文経典と散文経典を明確に区別し、四諦聖やサティ、修行法などに焦点をあて、原始仏教でも最も古い仏教を考察し、初期韻文経典の段階で教理化が進められていったことを明らかにした画期的書。
目次
第一章 四聖諦と三学
第二章 「苦しみ」と「苦しみの起こるもと」
第三章 「自己の存在に対する正しい自覚」の宗教的意義
第四章 修行法の展開―三学と三十七道品
第五章 三宝の成立と「信(saddh ̄a)」の用法
第六章 ゴータマ・ブッダの教え―宗教実践から教理化への一断面
著者等紹介
並川孝儀[ナミカワタカヨシ]
1947年京都府生まれ。佛教大学大学院博士課程満期退学。インドのジャワハルラル・ネルー大学客員研究員、同客員教授などを経て佛教大学教授。博士(文学)。現在、佛教大学名誉教授。専門はインド仏教、とくに原始仏教、部派仏教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
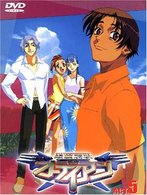
- DVD
- 銀装騎攻オーディアン ACT.5