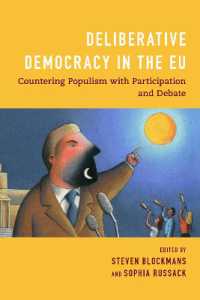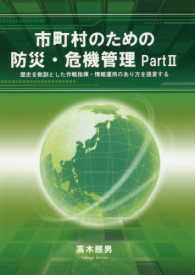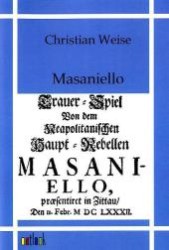内容説明
冠動脈インターベンション、冠動脈バイパス手術・薬物療法、心臓リハビリテーション…治療の最前線から食事改善、運動法、発作回避の心得まで。
目次
第1章 狭心症・心筋梗塞とは?(心臓のしくみと主なはたらきを知ろう;狭心症には2つの種類がある ほか)
第2章 狭心症・心筋梗塞の治療法(発作がおきたときの対処法;からだへの負担が少ない冠動脈インターベンション ほか)
第3章 これ以上進行させないための食事療法(1日の塩分は6g未満にする;健康的にやせるための食べ方 ほか)
第4章 発作を防ぐ、病気をよくする生活法(健康的にやせることがいちばん;病気を抱えた人の運動習慣のつけ方 ほか)
著者等紹介
相澤忠範[アイザワタダノリ]
1942年生まれ。1966年福島県立医科大学卒業。東京医科歯科大学医学部付属病院、平塚市民病院循環器科を経て、1979年より(財)心臓血管研究所付属病院に勤務。2005年より心臓血管研究所所長。専門は虚血性心疾患、心臓カテーテル、冠動脈インターベンション。また「ハートケア情報委員会」を設立し、委員のひとりとして、狭心症や心筋梗塞の情報提供をしたり、早期予防、早期発見と治療、再発防止を一般に広く呼びかけている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
wiki
6
図解を中心としているので内容はわかりやすい。とにかく心臓に負荷をかけないことが大切で、その手法というのは寒暖差、ストレス、感情の起伏など、自ら注視していれば体感的にわかるもの。過度なストレスに晒されているというのは自身もその通りで、休日などはコーヒー片手にソファで本を読みふける生活をしているのは、こうした身体的負荷を軽減させる方法を無意識に選択していたとも考えられる。今日はこれが食べたい、と思う時もだいたいその栄養素が足りない時。身体は正直なのだ。持ち主が、身体からの信号を聞けているかどうかなのだろう。2018/07/10
蒼姫
0
狭心症・心筋梗塞以外にも、食材に関することや、運動の仕方、トイレでのトラブルを避けること、水分対策、入浴法などなど。 色々とためになることが盛り沢山!! 【図書館】
-
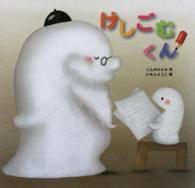
- 和書
- けしごむくん