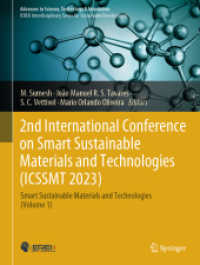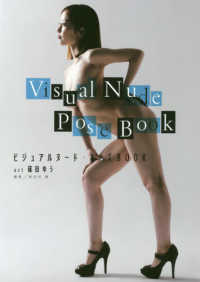出版社内容情報
一期一会の文化?
茶の湯は五百年の歴史を持つわが国の代表的伝統文化の一つです。中国から禅宗の僧侶たちによって伝えられた時は、庶民には関係のない飲み物であったものが、利休の出現によって、茶は庶民のものへと変わっていきました。
江戸時代に一般化された「茶飯事」という言葉がある。これは、ごくありふれた、くり返される事柄をいい、例えば、茶を欲む、客に茶をすすめるという日常的な事柄である。
しかし、生活文化が向上していくにつれて、このありふれた行為、行動にも規則や理念が求められるようになった。「茶の湯」がそれである。
本書は茶のルーツ、茶の湯の歴史、とりわけ利休による茶の湯の大成まで、その美意識・理念の転換のトレイス、禅宗との関係と作法・礼法などが語られている入門書。
-----------------------------------------
茶といえば、普通常用されるのは緑茶である。これを臼で挽(ひ)き抹茶としたものに挙措(きょそ)、作法が加えられ「茶道」という伝統文化となったのは何故だろうか。
いうまでもなく茶の発祥地は中国。すでに二千年前に茶が飲まれていたという資料がある。唐の文人、陸羽(りくう)が書いた『茶経(ちゃきょう)』は、世界で最初に書かれた茶の専門書といわれている。この『茶経』の出だしに「茶は南方の嘉木(かぼく)なり」とあるから、茶のルーツはおそらく雲南省辺りではないかといわれている。
唐では飲茶の習慣が広がり、茶に税がかけられていたといわれるほどであった。
日本に最初に伝えられたのは、遣唐使の留学生たちが持ち帰った「団茶(だんちゃ)」というもので、これは、茶の葉を乾燥して固めたものである。しかし、持ち帰られた団茶は発酵臭が強く、日本人の口に合わなかったようである。
それから四百年後、鎌倉時代になって、入宋していた栄西禅師によって抹茶(まっちゃ)法が伝えられる。ここに初めて、現在の茶の湯につらなる飲茶法が日本にもたらされたのである。
内容説明
茶飯事から、茶のルーツ、「和敬清寂」への道をたどる…。
目次
お茶と生活
「数奇」から「道」へ
茶をめぐるルーツ
茶の湯におけるバランスについて
茶の湯の「美」について
茶の湯における理念の転換
文化としての礼法
著者等紹介
川西洋子[カワニシヨウコ]
1971年東海大学教養学部生活科学科卒業。1999年北京社会科学院客員教授。現在、東海大学短期大学部助教授。2001~2002年ベルリン自由大学で日本文化論と茶の湯を教える
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。