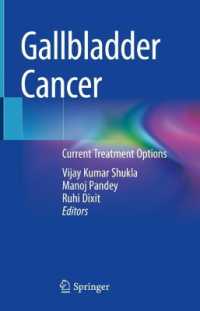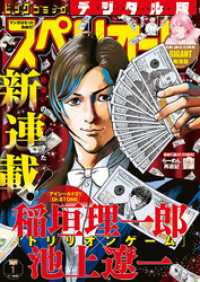出版社内容情報
イラン国民はホメイニーの指導の下シャー体制を打倒。ホメイニーが無敵と謳われたイラン皇帝を打ち倒しえたのは? このホメイニーとはどういう人物? 中東記者が信憑性の高い資料と取材をもとにその謎に挑戦。
ホメイニー ―おいたちとイラン革命― 目次
1.忽然と現れた一宗教者
2.父の虐殺
ロレスターンの荒野で/イスラームのマハトマ・ガンジー/アラークから向けられた追手/遺児ルホッラー・ムサーヴィーの教育/聖都コムヘ出かける/ホメイニーという姓の由来
3.アッラーの戦士たち
シーア派の起源/イスラーム法学者、救世主・エマーム/神の正義は地上にありパハラヴィー朝のイスラーム政策/バハイ教徒を優遇するシャー/イランのユダヤ人たち
4.聖都コムでの研鑚
ミナレットとボーリング塔の聳える町/死者を輸入しモッラーを輸出する聖都/シーア派の財政機構/神学者ホメイニーの理念/圧政者への抵抗はモスレム第一の義務/遺言状をめぐる困乱
5.シャーの抵抗
モハマッド・レザーの即位劇/列強の操り人形/アメリカに賭ける/キュロスをもってムハンマドを制す/モサッデクの登場と亡命のリハーサル/進歩狂的独裁者
6.最初の一騎討ち
テヘランにあがる黒煙/恐怖と戦慄の秘密警察サヴァク/白色革命/圧政者に死を!/モスクに乱入する軍隊/牢獄に繋がれたホメイニー
7.亡命の途に
早暁の誘拐/トルコヘ連れ去られる/ホメイニーの名を抹殺する/ターバンのエピソード――モッラーの抵抗/イラクヘ移る/政治闘争への転換期、一九七〇年/ホメイニーとイラン・イラクの利害関係
8.シャーの罪業
西欧型進歩の陰で/イスラームによる民衆の自覚/カナットの崩壊/いびつな高度成長のもたらしたもの/パハラヴィー一族の栄華
9.動きはじめた暴力
息子を埋葬するホメイニー/揺れ動く皇帝の自由化政策/アーバーダーンの烽火/二週間の春風/ジャーレ広場の虐殺と全土麻痺のゼネスト/最後の防塁――軍事政権
10.革命の遠隔操作
リンゴの樹の下の老師/ホメイニーを怖れたクウェイトの首長/イラクを去る/カセット・テープの勝利/ホメイニーのブレインたち/フランス政府の打算/十八のペルシャ娘と「結婚」
11.シャーは去る
混乱と無秩序のなかで/巡礼に出かけるファラハ王妃/軍隊をからかう民衆/原油供与を受ける大産油国/出国を迫られた皇帝/テヘランのカーニヴァル――ホメイニー! ホメイニー! ホメイニー!
12.十五年ぶりの帰国
バハティヤールの空しい闘い/パリからテヘランヘ――機上のホメイニー/ホメイニーを迎える民衆の歓呼と熱狂/二人の首相――二人の友人/武器をとる民衆/「不死鳥」が死ぬとき
13.ペルシャ湾の憲兵は消えた
中近東最大の軍事力――フランケンシュタインの怪物/CIAの鈍感さ、アメリカの誤ったイラン認識/ソヴィエトの当惑/ターバンを巻いたカール・マルクス/近隣諸国への波及/スクラッフになるイラン軍
14.地上における神の国
コムの古い質素な家/モスレムの自発的な国家建設/イスラーム社会で勝利が意味するもの/イランに残された最後の拠り所/理念と現実のギャップ/主権者はアッラーなり
地図1(イランとその周辺)
地図2(イスラーム教の普及地域)
訳者あとがき
……著者ハインツ・ヌスバウマーは、オーストリアの日刊紙『ヴィーナー・クリール』紙上で中東問題に筆をとっているジャーナリストで、本書の記述からもわかるように、中東各地を取材して、相当なキャリアを積んでいる人だが、本書のようなブック・ジャーナリズムの著者として登場したのは、今回が初めてである。
ホメイニーが一九七九年二月一日にテヘランヘ帰還し、いよいよ革命の勝利が決定的となったころから、同紙上に彼が連載したスケッチ風の記事をもとにして書かれた本書は、燃えさかる時局的問題に対する速やかな対応ぶりと、他に類書がないところから、ドイツ語圏諸国ではかなり高い評価をうけ、今日なお広く読まれていると聞く。……
……本書の翻訳にあたったのは、アジア現代史研究所の伊丹一雄、奥野路介、田川恒夫、訳文の統一をしたのは田川である。
1981年春 田川恒夫