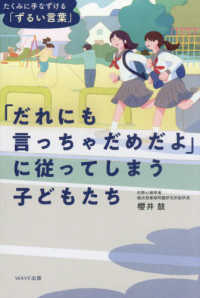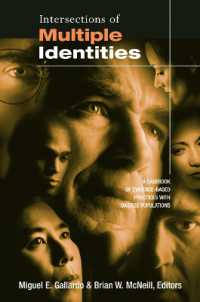内容説明
地図、ことばの仕組み、コミュニケーション、そして社会の変化から、ことばの地域差と日本の社会を考える。
目次
第1章 地図から見えることばの地域差
第2章 ことばの仕組みから見える地域差
第3章 コミュニケーションから見えることばの地域差
第4章 社会の変化から見えることばの地域差
第5章 「方言」から見える日本の社会
付章 調べてみよう
著者等紹介
木部暢子[キベノブコ]
国立国語研究所時空間変異研究系教授
竹田晃子[タケダコウコ]
国立国語研究所時空間変異研究系特任教授
田中ゆかり[タナカユカリ]
日本大学文理学部教授
日高水穂[ヒダカミズホ]
関西大学文学部教授
三井はるみ[ミツイハルミ]
国立国語研究所理論・構造研究系助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koning
16
一般教養的な軽い入門講座という感じ。ざっくりと日本語の方言を解説しつつ、更にどういう勉強をしたらいいか?と大学生あたりに読ませるつもりで書いた感じなのだけど、一般人で方言とか気になる!って人にもそんなに難しくなく読めていいんじゃないかと思います。ただ、図版で地図の塗りとか潰れてて判別できなかったりするので、巻末の参考文献を探して確認してねという感じなのが辛いかも。2013/09/29
gecko
10
「方言学」の入門書。図表が豊富で、方言研究の全体を概観できる。さまざまな観点から見ることばの地域差が扱われ、最終章では「方言コスプレ」など近年の動向にも言及がある。方言研究の社会的意義としては、医療に関する方言の情報提供などが挙げられる。西日本方言では「上向き待遇」の表現=敬語だけでなく、「下向き待遇」の卑罵表現も多様(サラス、ヌカス、シクサル)というのは納得。日本をヨーロッパの地図上に置くと、その諸方言はドイツ語とフランス語といった別の言語同士の関係に匹敵するという導入も印象に残った。 2013年発行。2023/03/09
SKH
6
序盤の各種データはほぼ未見で新鮮。2014/01/22
takao
2
ふむ2022/10/25
中村明裕
2
(#木部暢子ら2013)図版豊富で、眺めるだけでも楽しく勉強になる方言学入門書。半分以上を社会言語学や語用論的問題に割いていて記述的な話はわずか。比較方法にも言及がない。そのへんが時局に乗った新しい入門書という趣だけど、ちょっとさみしくもある。2013/12/28
-
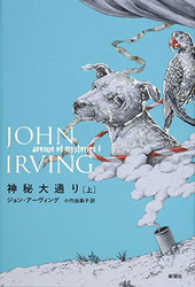
- 電子書籍
- 神秘大通り(上)