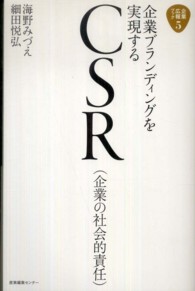出版社内容情報
2019年に刊行された『世界文学アンソロジー』の姉妹編。
1950年代以降に国語教科書に採録された外国文学作品から25編を厳選し、採録時にカットされた箇所も含めて収録。
各年代の採録作品を通して,当時の世相や国語教育を取り巻く状況に触れた解説やコラムも必見。
内容説明
「掟の門」「夏の読書」「ジュール伯父」「信号」「最後の授業」…。戦後の昭和~平成~令和に至るまで、時代を彩った世界文学の名作を教科書で採録されなかった部分も含めた“ノーカット”で収録。
目次
第1章 現代
第2章 九〇年代
第3章 八〇年代
第4章 七〇年代
第5章 六〇年代
第6章 五〇年代
著者等紹介
秋草俊一郎[アキクサシュンイチロウ]
1979年生まれ。日本大学准教授。専門は比較文学・翻訳研究
戸塚学[トツカマナブ]
1980年生まれ。武蔵大学教授。専門は日本近現代文学で、特に1920~30年代のモダニズム作家の表現や、作家の翻訳行為に関心を持っている。三省堂高校国語教科書編集委員を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
58
当時の情勢で消えたり、残ったりしたとは言え、学生が世界文学・詩・戯曲に触れるきっかけを教科書が作るとは、なんて贅沢なんだろう!実際、学生の頃は分からなくても大人になってからだと心に沁みる作品は結構、多い。因みに私は高校時代に教科書で魯迅の「ちいさな出来事」に触れた思い出があります。個人的に李正子さんの「<生まれたらそこがふるさと> うつくしき語彙にくるしみとじゆく絵本」という一句に胸を打たれました。また、「一切れのパン」が象徴するものは希望だったのだろう。そして「美人ごっこ」の幻想を打ち砕く真実の残酷さ2024/05/02
かふ
23
今の子たちはカフカ『掟の門』(没後100年で好きな作家だけど)なんて読まされるなんて人間不信にならないか?とか、90年代は尹東柱の詩が掲載されていたり(韓流ブームで今はほとんどこういう作品は掲載されないという)、80年代はラングストン・ヒューズとか(アメリカの黒人詩人)羨ましいと思ったり、私らのときはドーテ『最後の授業』(不変のナショナリズム)はやったなとか懐かしくなったり、魯迅は鉄板だなと思ったり、いろいろ興味深い。もっとも教科書に載るような作品なんて読みたいとも思わないんだろうけど。国内文学も知りたい2024/06/06
かもめ通信
22
『世界文学アンソロジー』の姉妹編。小・中・高の国語教科書に掲載された外国文学作品(一部日本語で書かれた作品を含む)の中から25人による27作品を集めたアンソロジー。90年代から50年代まで遡って10年ごとに4、5作品を紹介。年代毎にそれぞれの作品の特徴やその時期の学習指導要領の傾向などを紹介する解説がついている。作品をどう読ませるか、教科書で取り上げる意図はなにかという点に着目して、収録作品を改めて眺めてみると、単体で作品を読んだときとはまた違ったものが見えてくる気がして興味深かった。2024/07/08
くさてる
20
国語教科書に掲載された海外文学を27作品集めたアンソロジー。読んだ記憶のある作品はなかったけれど、添えられている解説などを読むと、国語の教科書にこめられた教育の理念に崇高なものさえ感じる広さと豊かさのあるアンソロジーでした。なにより傑作で粒ぞろい。強制収容から逃れようとする男の道行きを描いたムンテヤーニ「一切れのパン」ホラー短編集に収録されるのも納得のサンソム「垂直の梯子」悲しくて胸が痛むのにどこか温かいアルラン「降誕祭」しみじみと良いスタインベック「朝めし」などがとくに印象に残りました。2024/04/17
ひねもすのたり
10
1950年代から現在まで教科書に採用された翻訳小説を27編チョイスしたアンソロジー。 サスペンスフルな展開で最後のオチに教室がざわついた記憶のあるフランチスク・ムンテヤーヌの『一切れのパン』今読んでもやたら重苦しいアルフォンス・ドーテ『最後の授業』の二篇を教科書で読みました。 令和の現在掲載されているカフカの『掟の門』ワケのわからなさが良いですね。 それぞれに解説がついていて採用された時代背景やねらいについて書かれていて面白く読めました。★4 2025/04/04
-

- 洋書電子書籍
-
ピーター・パン物語集
The C…
-

- DVD
- カバーガール 深夜番組の天使たち


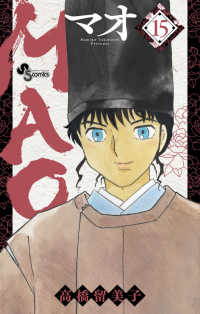
![字は1日でうまくなる! 水筆ペンセット [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40743/4074366835.jpg)