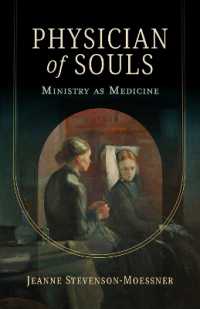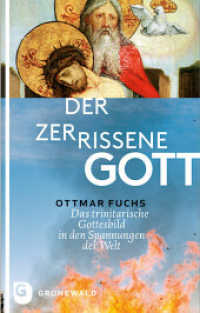内容説明
人とモノが行き交い、情報が駆けめぐる「巨大市場」江戸の実像。
目次
プロローグ 絹に支配された国
第1章 江戸年中行事
第2章 与力・同心と大縄拝領地
第3章 江戸の拡大「三田村鳶魚十四変」
第4章 天下普請と江戸で働く人々
第5章 都市の祝祭と劇場
第6章 寺と巡礼
終章 怒涛のような貨幣経済
著者等紹介
鈴木理生[スズキマサオ]
1926年東京生まれ。千代田図書館勤務を経て、東京都市史研究所理事。都市史研究家
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 英字新聞・単語倍増法