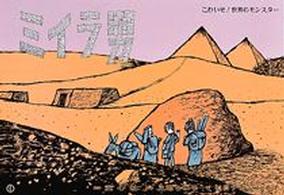内容説明
この本で第2次大戦の潜水艦のなかへ入り、そこで乗員がいかに働き、どのように戦ったのか、自分の目で発見してみよう。オールカラーの素晴らしい断面図が、潜水艦の構造と乗員たちの暮らしをいきいきと再現してくれる。
目次
最初の潜水艦
2つの世界大戦
潜水艦の設計
潜水艦の建造
潜水艦の内部
中央部
前端部と魚雷発射管
制服
寝ること、食べること
潜望鏡で
ソナー
潜水艦での生活
空気
ディーゼル・エンジンと蓄電池
大西洋の荒波との戦い
魚雷の搭載法
魚雷と大砲
大西洋の戦い、1940~43年
Uボートによる攻撃
人間魚雷
現代の潜水艦
年表
潜水艦の歴史
解説 潜水艦の発達と今後
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
acesmile@灯れ松明の火
4
戦時中の技術って今から見ればローテクですよね。そこが面白い。でも軍事に纏わるほとんどの事の基礎がこの時代に出来上がっているような感じさえ受ける。最初は誰が好んで潜水艦になんか乗るだろうかと思った。泳ぐ棺桶?だものw空気も悪そうだし、食べ物もろくな物が食べられなそうだし。魚取っても焼けないしwでも見えない事が圧倒的有利ということで戦歴を上げていったので乗りたい人も増えたのかな?紳士の国イギリスでは卑怯者扱いをうけていたがその有用性が解ると積極的に取り入れたって言うんだからイギリス人も結構チャッカリ物だねw2011/05/23
6haramitsu
1
図書館の子どもコーナーにあったけど、よく分かる。本当に兵器は非人道的。以前に宮崎駿の兵器の本でもそうだったけど、生存本能は様々な発明のモチベーションになるけど、戦争自体に勝者はない。戦争した時点で両者とも不幸。しかし、船や潜水艦は隔絶されているので、士官は大変だろうなぁ。バウンティ号の反乱みたいなこともあるし、水兵一人のミスで撃沈もあるし。結局、最後は人間関係だよなぁ。2024/12/31
-

- 電子書籍
- 毒より強い花【タテヨミ】第89話 pi…