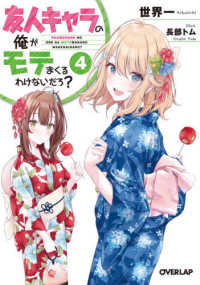内容説明
本書は、丸刈り・制服・バイク・パーマ裁判を通して、学校の実態と教育問題の根幹を明らかにする。
目次
校則裁判の示した課題
玉東中学校丸刈り校則事件(管理主義校則の根源―丸刈り校則;玉東中学校丸刈り校則事件のあらまし;第一審判決;判決を読んで ほか)
公立中学校制服事件(制服と制服裁判;千葉県大原中学校事件;京都市立神川中学校事件;制服は強制か、非強制か―「規制」概念について)
バイク規制校則事件(東京学館高校事件;大方商業高校事件;修徳高校〈男子部〉事件)
修徳高校パーマ退学事件(はみ出した生徒の非劇;一審判決―原告生徒敗訴;二審判決は一層学校寄り;パーマ校則事件の示した問題)
校則の現実と裁判官の思考(硬直した一般論;混乱する「自主退学勧告」概念;裁判官の生徒像の混乱;学校・教師の教育専門性と生徒の人権;校則裁判と親権)
最高裁の論理を超える(昭和女子大事件最高裁判決を見直す;部分社会論批判)
法と教育の間
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かみしの
6
レポート用。丸刈り事件、制服事件、バイク事件、パーマ事件と有名な4つの校則に関する教育裁判を取り上げ、その判決が抱える問題点を指摘する一冊。読んでいると結構いらいらします。いずれの校則も教育目的と照らし合わせれば不合理ではない、とされていますが、その論理基盤があまりにおそまつ。例えば丸刈りは、〈髪の手入れに時間をかけ遅刻する、授業中に櫛を使い授業に集中しなくなる〉だとか〈整髪料等の使用によって教室内に異臭が漂う〉のを防止するために制定されるといい、バイクの禁止は〈勉強にあてる時間を確保すること〉2012/08/01