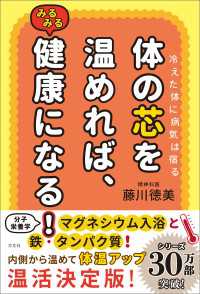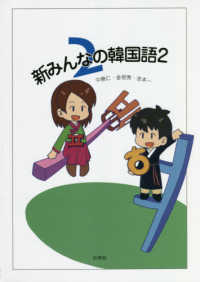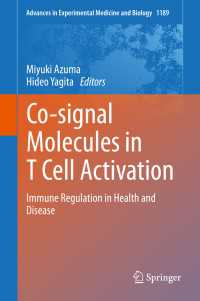出版社内容情報
落語家・立川談志師匠が1965年に初めて書き下ろした作品。最高傑作のロングセラー!落語家・立川談志師匠が1965年に初めて書き下ろした作品にして最高傑作のロングセラー!
その一 落語の観方聞き方
噺のおもしろさ
落語の落げ「地口落ち」「考え落ち」「見立落ち」「幽霊落げ」/落げの演出法/噺のスター/笑い三態とギャグ/ケチはケチなりに、泥棒は泥棒なりに/間抜けの楽しさ
寄席のエリート/講談と落語/落語のルール/郷愁と夢/素朴・正義感・四季/艶笑落語/艶物復活/女性は艶物がお好き/艶物の演出法/廓噺について/色物について/音曲について
その二 真打になるということ
浅草松竹演芸場/映画『大平原』に感激/多摩川園劇場/少年講談/寄席通い/はじめて志ん生を聞く/三遊亭歌笑の死/落語は非行化を救う/みっともないから、ヤメテクレ/
真山恵介さんとの出会い/小さん師匠の家/小よし誕生/ふしきな世界/前座・二つ目・真打/前座の修業/ワリの話/楽屋帳の話/落語の題名について/出番のやりくり/
予備出演ということ/師匠を真似ること/バケた林家三平/イジられる話/楽屋で博打はご法度/鯛焼に泣く/怒鳴られる奴ほどものになる/初高座/無言のルール/
噺のケイコ場/月謝なしに噺を教わる/十八歳で二つ目になる/自分の落語をつくりだす/湯浅喜久治とのこと/古典落語のセンスとトピック/妙な現代化はやめよう/
若手落語会/春風亭橋之助のこと/若手落語会の崩壊/若手試演会のこと/東宝若手勉強会をクビになる/落語錬成会のこと/ウエストサイド物語に感動/
アスティアにサインをもらう/タップダンスに熱をあげる/噺家とモダンジャズ/噺家芝居/大阪へ出演/石井均と松竹文化演芸場/梅田の花月/
西条凡児の漫談/真打の声がかかる/五代目立川談志の誕生/オレは真打だ
その三 昔の噺家・今の寄席
柳亭左楽・桂文治・三遊亭円歌のこと/謳いあげる春風亭柳好/落語ライブラリーの計画/ツバナレと入れかけ/三河島まつみ亭/千住の栗友亭・神田の立花亭/木馬館と麻布十番クラブ/
川崎演芸場のことなど/噺家に受けない麻雀/はじめての独演会/村田英雄さんの浪曲/「二人のシャンソン歌手と一人の落語家」/「女は風船そよ風まかせ」/楽しい夜のショー/
安上り勉強法/寄席ブームと「談志ひとり会」
その四 観客・芸・人気ないしは笑について
労音という名のお客/アートシアターという寄席/噺家の演出と創造/古今亭志ん生の芸について/愛される芸人とは/人柄と芸のきびしさ/落語の超越した笑い/
落語の笑いとギャグ/古典落語は泣いている/スパゲッティの伴奏/客席のエチケット/笑わせない工夫/いい笑いを教える/落語はどうなるか
その五 わたしの落語論
新作落語は落語ではない/上方落語と大阪の寄席/テレビ落語/落語家が売れるということーマスコミと落語/落語一筋は昔のこと/わたしたちの前にはマスコミがある/
二足の草鞋ははける/落語は果して大衆的か/芸の保護と大衆化/器用でないと生きられない/貧乏は芸を滅ぼす/無料でも客は客/現代の落語家
カバーおよび中扉カット:長尾みのる
目次扉および目次カット:橘右近
立川 談志[タテカワ ダンシ]
著・文・その他
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たくろうそっくりおじさん・寺
姉勤
hitsuji023
0607xxx
mintia