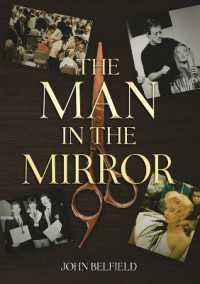内容説明
物価の優等生「牛乳」の影に潜む大きな矛盾。紙パックの牧場画に消費者は騙され、制度に押し付けられた借金に酪農家は苦悩し、狭い牛舎に閉じ込められ牛は病み衰えていく。唯一の解決は既存のやり方を根底から覆すこと。戦う酪農家が提唱する「山地酪農」。常識を超え、健康な牛を飼い、放置された山と森へ入れ!
目次
序章 呪われた「黒い牛乳」(牛乳の値上げに潜む秘密;牛乳パッケージの嘘 ほか)
第1章 歪んだ牛乳で誰が儲けたのか?(なぜ牛乳より水の価格が高いのか?;酪農家がはまり込んでいる負のからくり ほか)
第2章 機械仕掛けの牛たち―工業化した日本酪農の現場(日本の乳牛はほとんどがホルスタイン種;乳牛の飼料は二種類ある ほか)
第3章 日本の山林に生きる酪農(拡大造林政策の破綻と森林の逆襲;里山の荒廃が獣害を生む ほか)
第4章 日本酪農独立宣言(乳価の不足払い制度は限界に達した;それでもミルクチェーンから逃れられない酪農家たち ほか)
著者等紹介
中洞正[ナカホラタダシ]
1952年岩手県生まれ。東京農業大学農学部卒。酪農経営者。2006年より東京農業大学客員教授。山地に放牧を行うことで健康な牛を育成する山地酪農を確立した。山林・林野を活用した通年昼夜放牧を提唱し、酪農家の啓蒙に努めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
40
山地酪農を提唱した中洞正氏の著書。10年前の本だが、今も状況は変わっていないのではないだろうか?雪印乳業事件以来、衛生管理の強化は当然だが、新たに脂肪度の高い牛乳が大手メーカーにより推奨されると、その基準を満たすため栄養強化された輸入飼料を導入するしかない硬直性。飼料が高騰すれば酪農家の経営を直撃するが、もはや抜けることもできない。そういう固着した構造から抜けだし、人手が足りず放置された山林で牛を放牧し、結果として牛も健康になり、荒れた山林もまた生産に役立つサイクルに復帰できるという主張は爽快である。⇒ 2023/04/15
おはに
15
尊敬する中洞先生の著書。中洞牧場にお世話になったことがあり、その時受けた講義の内容より経営の話が主体。私の生前の年代や出来事の話が多く正直少し難しかったが、牛乳の種類や生産基準や牛については勉強したのでよかった。先生の話を聞いてから読んだので意図が大体理解でき共感できた。だが産業動物や牛乳の知識が薄い人の場合分かるのだろうか。でもアニマルウェルフェアという動物福祉の考えが広まりつつある世の中で山地酪農というあり方はとても今後重要になると思う。是非とも知らない人にこそ読んでもらい、もっと知ってもらいたい!2016/08/21
コサトン@自反尽己
7
非常に考えさせられる一冊。 普段我々が口にしている牛乳。その生産や流通の実態や内情が述べられている。 国や制度により、生乳量や効率が優先されてきた一方、牛の自由は牛舎により失われ、酪農家には多大な運営コストがのしかかっているのが業界の現実。 著者はそんな国や農協の方策と違い、自らの考えを信じ昼夜放牧・山地酪農を実践してきた一人。 著者の提言するように、経営方針を国が推し進めるのでなく、酪農家自らの判断・責任で選択出来る時代になることを願わずにはいられない。日本の森林、そして牛たちの為にも。【書】2009/12/13
けんとまん1007
6
牛だけでなく動物福祉という観点は、とてもわかりやすいポイント。日本の酪農に関する政策の脆さ・節操のなさがはっきりとわかる。そんな農政へ風穴をあける視点がここにある。2010/04/18
ケ゚ーコ
3
デパ地下で中洞牧場のソフトクリームを偶々口にする機会があり、どことなく薄っすら緑がかっていて、さっぱりした味で今まで食べたことない味でした。牛乳が手元に届くまでこんなに牛さん達や酪農家達が大変な思いをしているとは。心して飲まなければいけないのでしょうが、逆に飲むのが怖くなったのが本音です。牛が可哀そう・・・。2016/11/24