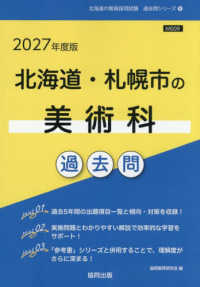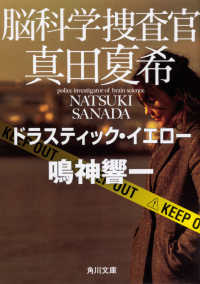出版社内容情報
NYタイムズではアート関連の記事が頻繁に1面を飾るなど、アートは欧米エリートにとって不可欠な教養である。他方、日本でそのようなことはなく、アートに対する扱いの差が、まさに欧米と日本のイノベーション格差の表れであると、世界97カ国で経験を積み、芸術系大学で教鞭をとる元外交官の著者は言う。アートに向き合うとき最も重要なのは、仮説を立てて思考を深めることである。そこで本書ではアートを目の前にして、いかに問いを立て、深い洞察を得るかについて解説。読み終わる頃にはアートの魅力が倍加すること必至の一冊
内容説明
NYタイムズではアート関連の記事が頻繁に1面を飾るなど、アートは欧米エリートにとって不可欠な教養である。他方、日本でそのようなことはなく、アートに対する扱いの差が、まさに欧米と日本のイノベーション格差の表れであると、世界97カ国で経験を積み、芸術系大学で教鞭をとる元外交官の著者は言う。アートに向き合うとき最も重要なのは、仮説を立てて思考を深めることである。そこで本書ではアートを目の前にして、いかに問いを立て、深い洞察を得るかについて解説。読み終わる頃にはアートの魅力が倍加することの必至の一冊。
目次
第1部 理解すると視野が広がる、アートの基本(アートがもつ「3つの効能」;日本人が抱く、アートへの「2つの誤解」;アートを“西寄り”にした世界五大宗教;西洋の“美的感覚”は、古代ギリシアとキリスト教から生まれた)
第2部 西洋アートから民族を読み解く(西洋アートの誕生の地―地中海ヨーロッパ;勤勉で緻密で先進的―北部ヨーロッパ;コンプレックスと抑圧―ロシアと東ヨーロッパ)
第3部 現代アートの底力(国を越え、力を畜えるアート―ユダヤとその歴史;宇宙の真理と未来志向―イスラム圏;略奪されても息づくアート―アフリカ ほか)
著者等紹介
山中俊之[ヤマナカトシユキ]
著述家・ファシリテーター。芸術文化観光専門職大学教授。神戸情報大学院大学教授。株式会社グローバルダイナミクス取締役。1968年兵庫県西宮市生まれ。東京大学法学部卒業後、1990年外務省入省。エジプト、イギリス、サウジアラビアへ赴任。対中東外交、地球環境問題などを担当する。2024年現在までに世界九十七カ国を訪問し、先端企業から貧民街、農村、博物館・美術館を徹底視察。京都芸術大学卒(芸術教養)。ケンブリッジ大学大学院修士(開発学)。高野山大学大学院修士(仏教思想・比較宗教学)。ビジネス・ブレークスルー大学大学院MBA。大阪大学大学院国際公共政策博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
ta_chanko
Nobu A
大先生
die_Stimme