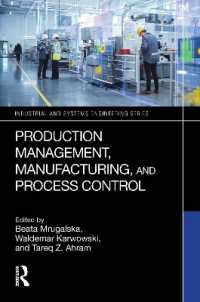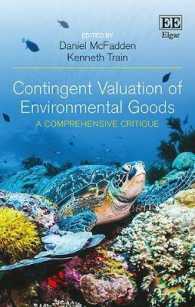内容説明
隻腕ながら遊撃隊長として榎本武揚とともに戦い、二十六歳にして五稜郭で散った伊庭八郎。死の五年前の一八六四年、伊庭が将軍・家茂の京都上洛に帯同した際に記した日記がある。その「征西日記」には、勇ましいタイトルとは裏腹に、伊庭が呑気に京都を食べ歩く日常が綴られている。ある日はうなぎに舌鼓を打ち、ある日は赤貝を食べ過ぎて寝込んでしまう―。本書では初めてその全文を現代語訳し、当時の政情・文化に照らし合わせ、詳細な解説を加えた。殺伐とした幕末京都を訪れた幕臣のリアルな日常が実感できる、稀有なる一冊である。
目次
第1章 将軍とともに上洛―元治元年(一八六四年)一月~二月(将軍警護の上京;澤甚のうなぎは都一番 ほか)
第2章 天ぷら、二羽鶏、どじょう汁―元治元年(一八六四年)三月(天ぷらを催す;桃の節句 ほか)
第3章 しるこ四杯、赤貝七個―元治元年(一八六四年)四月(加多々屋のうなぎ;鮎の季節 ほか)
第4章 京から大坂へ―元治元年(一八六四年)五月(小倉百人一首;菖蒲の節句 ほか)
第5章 お役御免―元治元年(一八六四年)六月(上る三十石船;池田屋事件 ほか)
著者等紹介
山村竜也[ヤマムラタツヤ]
1961年東京都生まれ。歴史作家、時代考証家。多くの時代劇作品の考証を担当する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なにょう
37
今で言うなら大卒か。大学生か。ハタチすぎた剣術一家のぼんぼん。1864年の家茂公の上洛に付き従う。お役目は数日に一回、京・大阪・奈良を巡る。お気楽に見えて、まさに時代の転換期。滞在の終わりには池田屋事件も起こる。★当時の人の達者なこと。大阪-奈良間(九里)を平気で踏破する。一方でしょっちゅう何かしら寝込んでいる。弟も旅の途上で体調崩して亀山で寝込んでいる。困った時はお互いさま、みんな情が厚い。★庶民の暮らしよう分かる日記は良いね。2019/10/14
いちろく
34
紹介していただいた本。将軍家茂が上洛した際に護衛として随行した伊庭八郎の半年間の日記。「征西日記」と記された内容は、京都各地への遊行や食べた物などが中心の日常が描かれていた。時は、幕末の京都。動乱の時期でもあるはずなのに、日記から漂う佐幕派武士の穏やかな雰囲気にはギャップを感じた部分もある。5年後に五稜郭で命を落としている点を含め、半年間の京都の期間は八郎にとっても特別な時であった事も伝わる。2022/01/01
えみ
29
時は動乱、幕末。佐幕と倒幕が激しく刀を交える時代。殊更に京では混乱を極め、熱き漢たちが力戦奮闘。命を燃やしていた‼…と興奮して語ったことを大いに後悔する、伊庭八郎の日記「征西日記」を読む。余りの“のほほん”ぶりに脱力。もう笑うしかない!笑って泣ける!5年後の壮絶な彼の戦いを知っているだけに。ただ能天気に京観光やグルメを楽しみ1864年あの「池田屋事件」があった同じ京の滞在記とは思えない日々を書き記す伊庭の無邪気さ、愛すべき人物。天麩羅パーティー、お気に入りの鰻とおしるこ、鯛は幾度も食す。幕末グルメ王見参!2020/06/14
mam’selle
28
徳川家旗本の関西グルメ観光日記。ただ外食の値段が非常に高い。鰻や鯛どじょうや天ぷらなどいずれも数千円から1万円超が殆ど。逆に現代の方が外食は安いような気がした。 4日に1度のお勤めでは将軍の道中警護や不寝番、剣術稽古も欠かさず一生懸命な21歳の若者の青春が描かれる。徳川家茂は度々御所で開かれる深夜2時までのパーティーや旗本の剣術総覧、大阪湾沿岸では泊まりがけで軍艦を閲兵などイベントが連続していた様子がサラリと描かれている。家茂が若くして亡くなったのもうなづける激務ぶりに驚いた。2020/06/26
onasu
28
幕末の京と言えば、尊攘派と幕府方との争乱の巷で、実際この日記の筆者伊庭八郎も幕臣として、14代家茂公に供奉しての半年間の滞在なのだが、書かれているのは、観光に食べ歩き、知己との往来と物見遊山の旅のよう。 いわば出張なんだけど、勤務日(二条城に詰めたり)が4日に一度、おまけにタフなんで、夜勤前や夜勤明けにも出掛けている。その合間にというか、流石は剣術家、剣の稽古は頻々と。 だが、この僅か数年後には転戦の末、函館五稜郭で討ち死にの定め。そのギャップもおもしろいが、日記の内容は単調なんで、少々飽きてはくる。2017/09/06