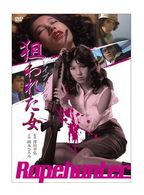内容説明
「日本語は曖昧で非論理的」「日本人は無宗教」「罪ではなく恥の文化」…わが民族の独自性を説いたいわゆる日本文化論本は、何年かに一度「名著」が出現し、時としてベストセラーとなる。著者はある時、それらの学問的にデタラメな構造を発見した。要は比較対象が西洋だけ、対象となる日本人は常にエリート、歴史的変遷を一切無視している、のだ―。国内外の日本論に通じる著者が『武士道』に始まる100冊余を一挙紹介、かつ真偽を一刀両断。有名なウソの言説のネタ本はこれだ。
目次
第1章 西洋とだけ比較されてきたという問題―『「甘え」の構造』『ものぐさ精神分析』など
第2章 「本質」とか「法則性」の胡散臭さについて―それはヘーゲルの『歴史哲学』から始まった
第3章 日本文化論の“名著”解体―『陰翳礼讃』『タテ社会の人間関係』『風上』など
第4章 「恋愛輸入品説」との長き闘い―『「色」と「愛」の比較文化史』批判
第5章 「日本人は裸体に鈍感」論との闘い―『逝きし世の面影』批判
第6章 天皇制とラフカディオ・ハーン―日本文化論の背景を探る
著者等紹介
小谷野敦[コヤノトン]
1962年生まれ。本名読みあつし。比較文学者、作家。東京大学英文学科卒、同大学院比較文学比較文化専攻博士課程修了。学術博士。『聖母のいない国』(青土社、河出文庫、サントリー学芸賞受賞)など著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
55
一面的なものの見方や、盲目的な西洋礼賛への批判など、納得することしきり。2018/02/10
ふみあき
40
超歴史的な文化的連続性を前提としたり、また階級というファクターを考慮に入れなかったりする日本人論は全部インチキだ、という主張の本。よく言われる「日本語は曖昧で非論理的」なんてのもステレオタイプで、生成文法派のチョムスキーによると、あらゆる言語は普遍的な構造を有しており、だから日本語が他の言語に比べて特に難しいということもない。渡辺京二の『逝きし世の面影』を読んだ西部邁が、古き良き日本を思って泣いたという話も出てくるが、休日も福祉も医療もなくて、死ぬまで働き通しの前近代的の庶民の生活など悲惨としか思えない。2022/09/16
金吾
28
痛快に感じる話と同じ穴の狢だと感じる話が混在しています。論文で地道な実証+おかしな意味づけ等は正にその通りだと感じました。個人にしても集団にしてもアイデンティティを保つためには他と違うことを強調するわりには独りよがりな部分が多いことや絶対的な真理はほぼないことから推察しますと日本文化論がある側面から見ればデタラメだと一刀両断できることは当たり前かなと思えました。2022/01/21
harass
25
ベストセラーなどでよく見る日本文化論本についての批評。『日本は海外のと比べてああだこうだ』と主張する本を学問的な厳密さからみて作者の無知や思い込みや意図からのおかしさを指摘する。著者のほかの本と重複するところがある。「恋愛輸入品説との闘い」(恋愛は明治期に輸入されたのでそれ以前には存在しなかったという俗説への論駁)や小泉八雲の実像と評価などが後半中心。かれの新書にしては良いほうだと感じた。それでもサービス精神なのか余計な雑談のような散漫な部分や個人的な感情がむき出しの部分が多いのはいつものことだが。2014/09/18
謙信公
20
「日本語は曖昧で非論理的」「日本人は無宗教」「罪ではなく恥の文化」など、日本人の独自性を説いた学問的根拠のない「日本文化論」本を徹底批判。ベストセラーになったり、名著と言われることが厄介なところ。これらの「日本文化論」は、西洋への憧れと自国愛との板挟みにあってすがる、というもの。本来、日本に生まれて日本語で育った人に「日本人としてのアイデンティティ」なんて関係ない。インチキ文化論の大本、歴史を法則化したヘーゲルは罪、ヴェーバーは宗教還元論者とバッサリ。著者お得意の恋愛論や裸体についても2章設けられている。2023/09/07
-
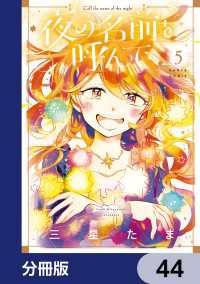
- 電子書籍
- 夜の名前を呼んで【分冊版】 44 HA…
-

- 電子書籍
- 千の星より、君だけが欲しい。 第46話…
-
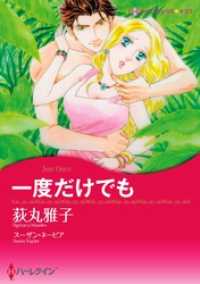
- 電子書籍
- 一度だけでも【分冊】 5巻 ハーレクイ…
-
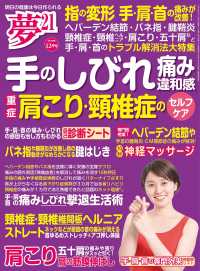
- 電子書籍
- 夢21 2019年12月号 WAKAS…