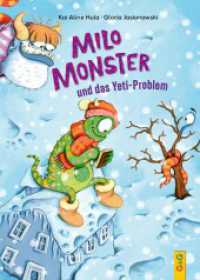内容説明
Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術)、Mathematics(数学)―これ1冊でSTEAM教育のすべてが分かる!アメリカでも大注目の最新教育法とその実践法。
目次
1章 STEMはなぜSTEAMになるべきか
2章 科学は芸術と創造性について何と言っているか
3章 芸術とSTEMで織り成すことについてよく尋ねられる質問
4章 芸術の織り込みを初等学年(K‐G4:幼稚園から小学4年)で実践
5章 芸術の織り込みを中等学年(G5‐8:小学5年から中学2年)で実践
6章 芸術の織り込みを高等学年(G9‐12:中学3年から高校3年)で実践
7章 科学・技術・工学でのSTEAM授業計画の増進剤
8章 数学でのSTEAM授業計画の増進剤
9章 全部まとめて考える
著者等紹介
スーザ,デビッド・A.[スーザ,デビッドA.] [Sousa,David A.]
教育学博士(Ed.D)。教育神経科学における国際的なコンサルタントであり、脳研究を学修改善の方略に変換する著書を十数冊以上著している。アメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、アジアを通して、20万人以上の教育者に研究内容を紹介してきた。高等学校で化学を教育し、学校の最高責任者を含む管理者として勤務してきた。シートン・ホール大学の教育系の非常勤教授、ラトガース大学の客員講師であった。科学に関する著書を編集し、先導的な雑誌に何十編もの論文を発表している
ピレッキ,トム[ピレッキ,トム] [Pilecki,Tom]
芸術学修士(M.F.A.)。フロリダ州のウェストパームビーチにある創造教育センターに12年間勤務し、元常任理事である。そこで100人以上の教育芸術家に対して専門的な研究成果を伝え、彼らがすべての科目の小学校、中学校教師が協働して教育できる準備を提供してきた。教育管理の分野で芸術学修士をもっている。合唱と器楽の教師であるとともに、元小学校の教師である。40数年間にわたり教育に従事してきた。その経験の中で、ニューヨークのサウスブロンクスにある聖オーガスチン芸術学校の創立者であり校長となった
胸組虎胤[ムネグミトラタネ]
1956年埼玉県浦和市(現さいたま市)出身、鳴門教育大学大学院学校教育研究科自然系コース(理科)教授。理学博士。群馬大学工学部卒業、筑波大学大学院化学研究科修了後、ソーク研究所博士研究員。筑波大学化学系助手、国立小山工業高等専門学校助手、助教授、教授を経て、2012年4月より現職。日本化学会化学教育有効賞、日本工学教育協会賞(業績賞)受賞。生命の起原および進化学会運営委員、日本教科内容学会理事。専門は化学教育、化学進化、ペプチド化学、立体化学。研究テーマは化学教育教材、化学進化とキラリティーの起源など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。