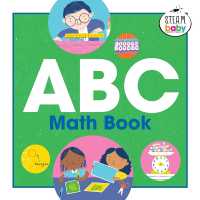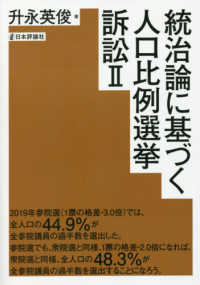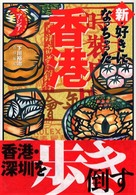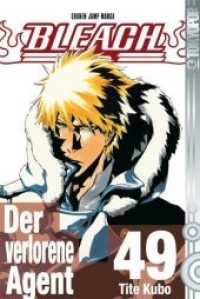内容説明
意外なものや、響きの美しいもの。変わった由来のもの。日本の生活に根ざした、知れば納得の「ものの呼びかた」集。
目次
第1章 この呼びかた、知ってますか?
第2章 厨にあるものの呼びかた
第3章 道具の呼びかた
第4章 自然がお手本
第5章 立場変われば、呼びかた変わる
第6章 古風なものの呼びかた
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
33
ものには名前があり、呼び方があるはず。現代の生活では使わなくなった物、馴染みのあるものなのにその一部を知らない物(針の耳)、生活の変化によって呼び方も変化した物(襟巻→マフラー)、などなど面白い例がたくさん挙がっている。私は、文様の呼び方の30余りにとても惹かれた。特に、「賽の目」という文様が気に入った。2020/04/05
ゆーり
15
教養本なんだけど、解説のコメントがちょっとくだけてて笑える。宅急便、エアーキャップ、セロテープなどは商標登録されているのは知ってたけど、エレクトーン、万歩計、セロハンテープまで登録商標だったなんて!一般名称も知らなかったものがあった。名前や名称が分かると、自分のなかに新しいものが存在し始めたという感慨がわく、って言葉には納得。2016/05/29
ぽけっとももんが
12
「呼び名がわからなければ、それらは存在しないも同然」「呼びかたを知ると、自分のなかに新しいものが存在しはじめたという感慨が湧いてきます」確かにその通り。それを認識していなくて会話にも乗せないなら知らなくても困らないかもしれないけど。着物などに使われる文様は名前も含めて素敵だし、コンパスを規(ぶんまわし)なんてあまりにもぴったりで誰かに教えたくなる。小さい頃近所の大工さんは墨壺を使っていたけれども、今ではそんな作業を目にすることもなくなっている。わたしの勤めていた百貨店も、ご不浄は「あたり」でした。2017/12/03
kuroi
10
日本人は昔からたくさんの美しい言葉を紡ぎ出してきた。しかしそれが今急速に失われつつある。文学はその日本の危機に歯止めをかける役割を担っている。驟雨、時雨、糠雨、俄雨……、雨一つにしても実に豊富な語彙をもつ日本語。しかしそれを知らなければ無いのと一緒ではないか。名前があるからこそ、存在するものもこの世にはたくさんあるのではないか。言葉は時代と共に変わっていく。しかし、失われつつある美しい言葉たちが未だにわたしたちの心に響く。わたしたちが守り、伝えていくしかこの言葉たちが生き延びる術はない。2018/12/27
長くつしたのピッピ
7
年齢を重ねても知らないことがたくさんあることに気づかされる本。ためになって面白い。2017/06/14